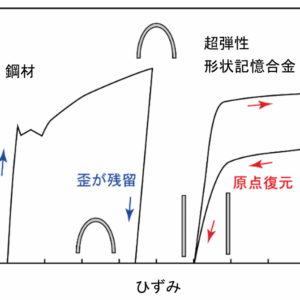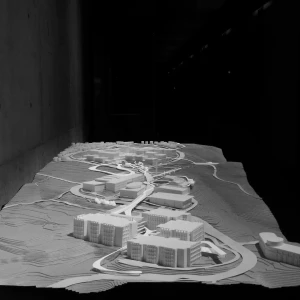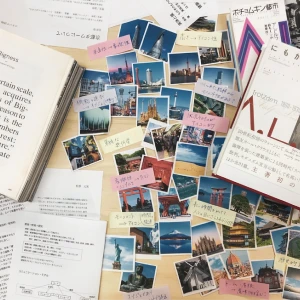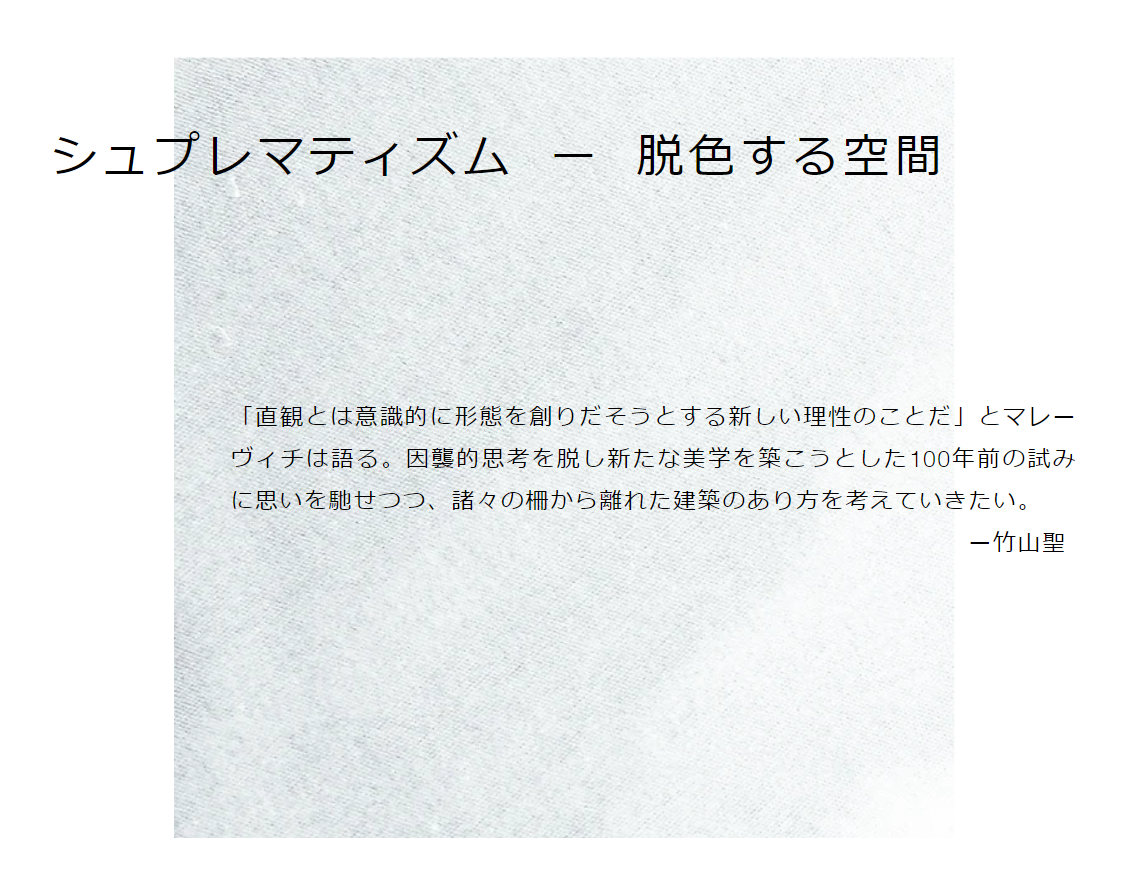
竹山研究室【脱色する空間】
本題では、以下のプロセスで設計をおこなった。
1.マレーヴィチの作品等からシュプレマティズムについて理解を深め、
「脱色する空間」という言葉を独自の解釈で定義する。
2.方位・等高線・道路以外の情報が隠された敷地において、
上記の定義に従って空間を設計する。
読書記録
カジミール・マレーヴィチ「キュビズム、未来主義からシュプレマティズムへー新しい絵画のリアリズム」「シュプレマティズム」『ロシア・アヴァンギャルド芸術』、J.E.ボウルト編著、川端香男里他訳、岩波書店、1988
竹山聖「形式化への意志と醒めた爽やかな楽観」『現代建築を担う海外の建築家101人』、鹿島出版会、1985
村上春樹『騎士団長殺し』新潮社、2017
セミール・ゼキ『脳は美をいかに感じるかーピカソやモネが見た世界』、河内十郎監訳、日本経済新聞社、2002
もくじ
→ カジミール・マレーヴィチとは
→ 「脱色」をめぐる言葉たち
→ それぞれの「脱色する」
→ 作品
→ 【エッセイ】竹山聖 「脱色する空間」
カジミール・マレーヴィチとは
ウクライナ・ロシア・ソ連の芸術家。キュビズムや未来派の強い影響を受けて派生した後、無対象を主義とする「シュプレマティズム」に達した。「White on White」など意味を徹底的に排した抽象的作品を追求しており、戦前における抽象絵画の一つの到達点でもあると評価されている。

「Black Square」(1915)

「White on White」(1918)
「空の青はシュプレマティズムのシステムによって征服され、漂白され、本当の永遠の概念を示す超越的な白」へと移行してゆき、そうして空色の背景から開放されたのである。」
第10回《国家展》によせられた声明文(1919年)
「画家は、もし純粋な画家たらんとすれば、主題と対象を捨てるべきなのである。」
「キュービズム、未来主義からシュプレマティズムへー新しい絵画のリアリズム」(1915年)
「脱色」をめぐる言葉たち
見慣れているのに、どんなものとも関連づかない。馴染み深いのに、どんな情景も呼び起こさない。意識の中にある繋がりを断つことによる驚き。
建築は形から脱しなければならない。
マレーヴィチがたどり着いた究極の脱色は「白の上の白」だろう。これ以上の抽象を求めても、その先に道はおそらくない。脱色されきった感覚を保ったまま新たな絵画を生み出そうとしたマレーヴィチの姿勢にならいたい。
直観の中に新しい理性の輝きがある。
白紙のキャンバスに描く絵画と、既に機能によって着色された敷地に設計する建築の差を考える。
プログラムを排除し建築を解放する。
合理性とは全体が織りなす秩序であり、非合理性とはそのものが持つ欲望である。