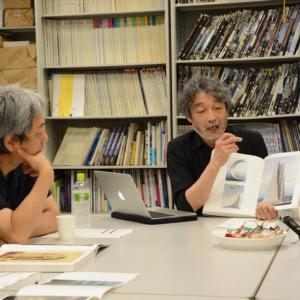鹿島建設/豊田郁美 | ” 建てる” という挑戦鹿島建設
2013年7月11 日 豊島美術館にて
聞き手 森下・阿波野・鵜川
記録 杉村・西尾
現代美術館において、アートは建築と融合して空間化される。その中にあって施工者は、発注者、設計者、職人、そしてアーティストと複雑に関わりながら空間を実現していく。地中美術館や豊島美術館で現場所長を務めた豊田郁美氏に、その実際を伺った。いかにして空間は実現されたのか。豊田氏が「奇跡」と表現された達成へは、関係と努力による「必然」的な道程があった。

家プロジェクト 『南寺』 Architect : Tadao Ando Photo : Tadasu Yamamoto
― 25 年目のプロジェクト
森下 豊島美術館(2010年開館)の建築プロジェクトにはどういったタイミングで関わるようになられたのですか。
豊田 ずっと最初から携わっています。西沢立衛先生(豊島美術館設計者)が福武總一郎会長(ベネッセホールディングス取締役会長)にプレゼンをしたとき、私はそれを横で聞いていたというぐらいですから。そして敷地をどう決めるかとか、大きさや環境、法的な話から、どうやって建物をつくるか、そして作品をどうやってつくるかということまで、最初からずっと関わってきました。それは地中美術館もそうです。最初から最後まで見届けて、今もメンテナンスのことについてずっと関われるということは、ある意味ではすごく幸せなことでしょうね。例えば物をつくっていて、図面があって、前後はわからないけれども、ただつくれと言われて「つくりました、終わりました」。これは非常につまらない。私は設計図を作る段階から関わっていますから、どういう形にするのかに携わって、つくって、その後どうやってこれが老化していくかっていうことも踏まえてみていく。それはすごく幸せなことだろうなって思います。同時に大変なことでもあるのですが。そういう経験をしている方は、他にはあまりいないでしょうね。
森下 直島での一連のプロジェクトはどれも最初から関わられたのですか。
豊田 全部最初からです。途中からという建物はないです。最初の「何をつくる」、そして「設計者は誰」、「どこに」、「いくらで」、「どういう作家で」という会話から始まります。先日、新聞に出雲大社の改修をずっとやっている監督(清水建設、金久保仁)さんが載っていましたが。あの方も幸せなのだろうなあと思いましたね。あの方も最初のきっかけというのはたまたまだろうと思いますが。
こうして長いスパンでお付き合いさせていただくとそのぶんだけ要求はすごくなりますが、やはり「競争の原理」は働きづらくなりますね。競争で安い、高いという話じゃない。この建物も元々「なんぼでできるかな」、「んー、~~円くらいでしょうかね」、というところからの話です。その上でぎりぎりのところで、下請業者や作業員の人たちも、無駄のない支払いになんとかまとめようとしているという状況です。
今日も美術館の開館前の清掃作業で、たくさんのスタッフの方々が丁寧に清掃をされていたのを見られたかと思いますが、こうやってしっかりと使っていただき、うれしいと同時に頭が下がります。
森下 豊島美術館の建設プロジェクトでは、皆さんが有機的に全体に関わっている、という意識があるように感じました。
豊田 結局私が手でつくるわけではないですから、常に職人というか、手を動かす人、要するに私の周りの色々な人に声をかけて、一緒に作り込もうという意識を持っています。最終的には頓挫してしまう場合もあるんですけれども、それ以上に最初からとにかく自分の気持ちの中でのチームを作っていって、やっていけばその職人の気分も高まる、ということになる。ですが、それは私が長いスパンで関わっているからできることです。急に「こんな建物をすぐつくれ」と言われてもなかなかできないでしょうね。だから、どうしてもつくるためには時間がいるわけです。
日本の場合いろいろな状況がある。例えばまず設計図があって、妥当性をとるために競争の原理を働かせてその中で一番安いところを選んでやるというように。するとそこには作り込みの思想がなかなか入ることができないでしょうね。それは良い面も悪い面もあると思うんですよ。つくったものに対してのこだわりなどは薄れると考えられますが、その分だけ値段というか金額の妥当性はとれるかもわからない。
しかし、そのようにして、あまりにお金が先立って設計者とつくる側が「お金がかかるからできない」とかいう話になると、これは非常につまらない話になってくる。特に最近、そのようにして作り込みに対する意識が薄れてきたと感じますね。
直島に私が関わり始めたのが平成元年(1989年)です。最初はキャンプ場をやり、25年くらいの間にいろんな建物をやって豊島美術館へという流れです。そしてその中で同時に作品の設置についても、ダン・グラハム、ブルース・ナウマンや、ジョージ・リッキー、大竹伸朗とか、そういった方とずっと関わりながらやっていました。
こうしてひとつの場所に携わり続けることができたというのはやはり幸せな話ですよね。けれどもその分だけいろいろ大変なこともありました。特に家プロジェクトの『南寺』(安藤忠雄設計、1999年竣工)は強烈に失敗しましたね。
― アートに誤差はない
豊田 ここでは何が作品のポイントかわからなくて作っちゃったんです。
展示しているのはジェームズ・タレルの『Backside of the Moon』という光を用いた作品です。作品として光をまわすために、空間全体をどうみせるかということが重要になっています。そのためにはすごく細部に渡って神経を使わないといけないんですが、特に作品の開口部のわずかなエッジの差で、その光が思うように出せなくなってしまうんです。ここで一番のポイントは、作品に開けられた四角い開口部のエッジなんです。
それを理解できずに、アーティストが「こうしなさい、ああしなさい」と言ってきたので「はいできます、こうやってこうやればいいんでしょ、まぁ大丈夫ですよ」という具合でやってしまったんですね。
アートの場合は建築の場合とは異なってザクッとした図面しかないから簡単に「つくっちゃえる」わけです。そのために重要な要素を見落として、間違いや失敗がいろいろありましたね。
例えば我々のものづくりには誤差があります。ですから「数字で何ミリ誤差があっていいんですか」と聞くわけです。すると「ノーノーノーノー、誤差とかそういう話じゃない。10mは10mで、5mは5mで、3mは3mだ」と。「いや3mでも誤差はあるんですよ」、「なにいってんだ、3mは3mだ」なんて。図面は出てくるから、そうつくったわけですよ。「じゃあどうしたらいいんですか」、とこちらは開き直っていくわけです。本当はそういう対応そのものが違うんだろうと今は思っていますが。
けれども、そういった経験の中で徐々に、作家が何を求めているか、じわじわとわかってきました。タレルさんがいっていることが、最後になって「あー、そうかな」、と思ったり。その後の同じく家プロジェクトの『護王神社』(杉本博司設計、2002年)のときもそうでしたね。
そうやって相手を理解し、様々なことをやるためにこちらとしても日本国内から世界中に至るまで、現地に実際に見に行くわけです。全て経験でしかないですから。例えば地中美術館(安藤忠雄設計、2004年。ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリア、クロード・モネの作品を収蔵)のときはこのときの教訓からジェームズ・タレルの作品を見に行きましたね。また、ウォルター・デ・マリアの『The Lightning Field』という、砂漠に1キロメートル四方に何本ものステンレス棒がずらっと並んでいる作品も見に行きました。すごいところでしたよ。そのようにして、今日もみなさん豊島まで来られていますけども、とにかく見る。それは安藤忠雄先生から教わりました。
地中美術館は上手く出来たかは別物として、頑張れたのはその前にこうして、いろいろな失敗や経験をしたからだろうなぁと思っています。
― 目地ひとつない美術館 ー地中美術館ー
豊田 地中美術館ではいろんなチャレンジをし、勉強させていただきました。
安藤建築というのはラインの組み合わせなんです。外の道路も含め散水栓から街灯、木の位置に至るまで全てグリッドで成り立っています。入り口のアプローチもグリットを意識して、作り込んでいます。そしてきれいなラインを出すために無駄なものや装飾は全て取り除くということになりました。新幹線というのはほとんどビスやボルトが隠されていて、乗っていても椅子の形、天井から、床まで感心するほどなのですが、そのようにして地中美術館でも部品を接続するボルトやビスをほとんど隠しました。
また打継ぎ目地も無くしました。外壁では普通、コンクリートは目地を5メートルおきにとる。それを一切全部なくしてしまったんです。またドアもドア枠をなくすためにコンクリート打設前に仕込み、コンクリートを打設した後で、また外すというようなことをしました。そうすると枠がなくなるんですよ。ガラスも、ガラスを入れた後でコンクリートを打設するとか、色々なことをやりました。また、照明の穴あけ一つにおいてもいろいろとこだわりました。

Photo : Mitsuo Matsuoka
そしてコンクリート打ち放しには漏水は致命的です。まして地下ですからね。地下水圧を落とすためにと、透水層を壁全体に設けています。これは手間がかかりましたね。また階段の打ち方においてもチャレンジをしました。モネの部屋も色んな事をやっています。そこでは壁や床、天井の作り込みはもちろんですが、展示ケースが最大の難所でしたね。どうやってモネの絵を額装するか。本来なら額縁屋さんに頼んで製作していただくのですが、当時学芸員であった秋元雄史さん(現、金沢21世紀美術館館長)から建物と一体となった額装にしたいという要求もあって、巨大なガラスをドイツから取り寄せたりもしました。
こうして、安藤先生と西沢先生という違いはありますが、地中美術館の経験があったから私もこの豊島美術館ができたというのがあります。