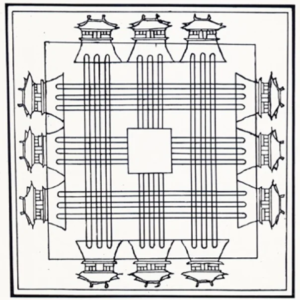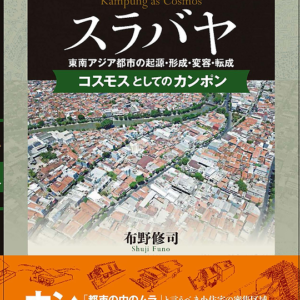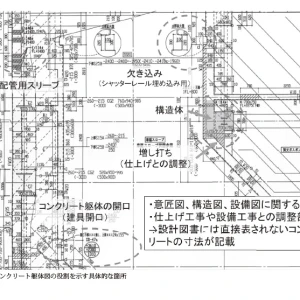建築に惹かれる|竹山 聖
Attracted to Architecture | Kiyoshi Sey TAKEYAMA
建築を考えるとはどういうことかを考える
『traverse新建築学研究』の今回の「惹かれる」というテーマに、ダイレクトに応じてみたい。
惹かれるには、モノに惹かれる、コトに惹かれる、ヒトに惹かれる、の三つがある。言葉も概念だからこの際コトに含めてしまおうと思う。
私がはじめて建築に惹かれたのは、モノにではない。ヒトでもない。何か特定の建築物が好きだったりしたのではないし、特定の建築家に憧れたわけでもなかった。
たとえば、法隆寺や薬師寺の塔や金閣寺に啓示を受けたわけでもなければ、小学校の時に訪れた代々木のオリンピックプールに、かっこいいとは思ったけれど、さほどグッときたわけでもない。1970年に千里丘陵で開かれた万博も、ちょうど高校に入学した年で、自宅が近かったのでよく夜間割引を狙って自転車で訪れたものの、立ち並ぶ建築物に感銘を受けたりはしなかった。むしろカンナムシリーズのオレンジ色のマクラーレンや白いシャパラル、あるいはフェンダーのストラトキャスターの方に関心が向いていた。この「妙に心にひっかかる形」をめぐっては、六耀社から1990年に出版された『KIYOSHI SEY TAKEYAMA:ARCHITECT』(数年前に22世紀アートから電子書籍『空間加工のイメージ:竹山聖のスケッチと言葉』として復刻された)に「ウェッジシェイプとサイの角」や「フェンダーのストラトキャスター」と題されたエッセイが掲載されている。モノとしては、むしろ車や楽器の方に惹かれてきたのだ。

ヒトについてはどうかというと、当時ネスカフェのゴールドブレンドのTVコマーシャルに清家清などの建築家が出てきていたけれど、何をしている人たちなのか、さほど関心を持つことはなかったし、京大に入ってすぐの「建築概論」という授業で、西山夘三先生が、知っている建築家の名前を書け、というアンケートを取ったときにも、丹下健三をあやまって丹下健三郎と書いてしまったほどだ。このことはのちに丹下先生の最初の奥様やそのお嬢様にお会いしたときにエピソードとしてお話ししたらお腹を抱えて笑われて、いいわね、その話、使わせてもらうわ、と言われた。それほどに建築の世界にも無知だった。
ではきっかけはなんだったか。ぼちぼち将来の進路も考えようかなという高校の頃、バスケットボール部の一年上に「京大建築」を志望する先輩がいて、「建築」という言葉の響きや、その示唆する概念や世界の広がりに何かしら直観的に心に響くものがあった。そこで実際にカリキュラムを調べると、彫塑実習・絵画実習や西洋建築史・東洋建築史・日本建築史、などがある。芸術的であったり文系っぽくもあったり。また父の尋常中学と高校の後輩であった金多潔先生に会いに行って話を聞いたら、とてもやりがいのある面白い分野ですよ、という言葉をもらったりして、まあとにもかくにも色々な分野に開かれている気がして、だんだん心が傾いていったわけだ。しかし「惹かれた」という状態になったわけではない。
はっきり「惹かれた」という状態に陥っていくきっかけは、今思えば京大新入生歓迎の会で、増田友也先生が半ば赤みのさした顔でグラスを手にこう語ったときであったかもしれない。
「建築を考える、とはどういうことか、を考えてほしい」と。
そのときはこちらも酔っ払っているから朦朧とした頭で、いったい何を言っているのだろう、という程度の理解だったが、そして多分ほとんどの同級生たちも狐につままれたような顔をしていたので似たり寄ったりだと思うのだが、少なくとも惹かれる伏線は張られていたのだと思う。1973年のことだ。
建築とは物でなく事であり、考えることそのもの
その言葉がまったく理解できなかったにしても、その問いかけは心に残った。そして設計演習が始まり、さまざまな講義や演習がおこなわれて、曲がりなりにも自分自身で考えていくきっかけが与えられていく。
設計演習の最初の課題は「場所の構成」というテーマだった。公園の一角に20M×20Mの敷地が与えられ、そこに「意味ある場所をつくれ」という課題である。「場所」とは何か、「意味」とは何か。「つくる」とはどういうことか。ここで、今よりもはるかに哲学的思索の雰囲気に満ちていた京大建築の傾向に触れることになる。
建築的思考のもろもろについては省くが、すっ飛ばして言えば、建築は名詞的ではなく動詞的に捉えるべきであり、すなわち建築とはモノでなくコト、「建築物」ではなく「建築すること」である、というのがそのエッセンスである。つまり、「物体としての建築」ではなく、「行為としての建築」が問われている。
このあたりのことについては、traverse編集委員会編の『建築学のすすめ』(昭和堂、2015)にも書いていて、繰り返しになるのでぜひそちらを読み直してもらいたいのだが、「建築」とは「つくること」であり、「つくること」をめぐる思考であり、設計の現場に根差した、さらにいうなら、身体に即して、頭だけでなく手に導かれた思考のことなのである。
「場所の構成」では機能だとかプログラムのある建築物を求められたわけではなかった。むしろ、壁や床などといった建築的なエレメントの配列を通して、空間、あるいは平面的に捉えればそれが場所になるのだが、ある意味を持った世界をそこに構成することが求められた。機能ではなく意味。建築が立ち現れるそのはじまりが問われている。これらも「建築学のすすめ」の繰り返しになる。けれども、重要なことなので押さえておきたい。
さてそのように、機能を持たない場所から徐々に機能を持つ建築へと、京大の設計課題は進行していく。これはかなり京大独自のことだったと思う。その後、東大大学院に進み他の大学でも教鞭を執ることになって痛感したのだが、ほとんどの大学の場合、住宅、事務所、美術館、学校、などというふうに建築物を機能別に分類して課題を出していく。機能の分析がそのまま建築の問題である、というふうに。もちろんそうした機能の分析は当然押さえておくべきあたりまえのプロセスなのだが、それがあまりに最初からパターンとして定型化され植えつけられていくと、そして使い方や工法上の便利さ、そして表面上の経済性(本当の意味での経済性はとても大切なのだが)の追求ばかりになっていくと、自由に空間の問題を考えていくみずみずしい創造的な芽も摘み取られていく。そんな恐れもなきにしもあらず、だ。
だから、1990年代に私が京大に着任し設計演習のカリキュラム編成をやり直したときに、建築の立ち現れるはじまり、つまり機能のない場所や建築をまずスタートラインに置き、かくなるうえでそれを徐々に変容させながら機能へと結びつけていく。すなわち、かつての建築的思考のトレーニングの道筋を、さらに明快な流れとしてカリキュラムに位置づけていったのだった。
ただしそれはだいぶあとになっての話だ。大学時代に話を戻そう。学生の頃はそんな自覚も思考も持ち合わせなかった。ただただ設計演習が面白く、これはかなり奥が深いものだ。学生のときの一種の思考ゲームとしてだけでもこんなに面白いのだから、実現する建築物に実際に関わったりすればどれほど面白いだろう、と感じもした。
しかし現実にこだわるばかりが建築的思考の対象ではない。建築の歴史を振り返るなら、実現されたものだけでなく、構想の段階の図面やスケッチが大きな影響を及ぼすこともある。例えば、ミース・ファン・デル・ローエのフリードリッヒ・シュトラーセのオフィスビルのスケッチ、あるいはエル・リシツキーの雲の鎧、そしてクロード・ニコラ・ルドゥーの理想都市のドローイングなど。そう、建築はやはりモノではなくコトだと捉えてもいいのではないか。
そして設計という行為の現場にあっては、つまり施工にとりかかる前の段階では、いまだモノとして実現していないのであるから、これは徹底的にコトの世界だ。いつかモノとなるやもしれないが、そして地球上に築かれる限り、重力にしっかりと抵抗して立ちあがる現実的なモノでなくてはならないが、そうした諸々の問題解決や配慮も含めて、あくまでも、いまだモデル化したり論理化したりするコトの世界にとどまる。建築を取り巻く他者(あらゆる事象)との関係は抽象化されている。
そこにはえてしてコトバが介在する。ただそのコトバは、ときに否定され、しかるのちにまたあらためて思考の手掛かりとして導入される、という複雑な過程をも内包している、そんなコトバだ。わかりやすくいうなら、言葉なんていらないんじゃない、という建築的アプローチもあれば、言葉や論理ですべてを語り尽くし表現し尽くせるはずだ、というアプローチもあるだろう。設計の現場ではよくあるやりとりだ。でも実はともに互いを必要としている。
さらに精確にいうなら、建築的思考はコトバを媒介としながらも、言葉では捉えきれないコトを、すなわち、ともすればすくい落とされがちなモノを、スケッチや図面や模型を通してすくいあげていく、そのような思考だ。建築に言葉は不要というのは傲慢だが、言葉で事足れりとするのもまた傲慢なのである。
建築に魅せられていた
かくして実際の設計の現場に立つ前のシミュレーションとしての設計演習が繰り返されていく。設計には無限の解があり、論理的であったり美的であったり、知的であったり感性的であったり、本物の建築物に比べれば小さな図面や模型を通して、身体をはるかに超えるスケールの空間を構想する。そうしたゲームにはまっていった学部時代を過ごしたあと、大学院で東大に行って原広司先生の研究室に入って、さらに本格的に建築に惹かれるようになる。そのようにして惹かれたこの建築という世界に、当然のことながらコトのみならず、モノもヒトも再び入り込んでくる。
1977年の大学院一年の夏休みにカナダとアメリカを旅して、ルイス・カーンの建築を見たときに、私ははじめて建築に、モノとしての建築に、惹かれそして感動した。最初に見たのはイェール大学のアートギャラリーとブリティッシュ・アート・センター、次にペンシルバニア大学のリチャーズ医学研究所、そしてキンベル美術館、最後がソーク生物学研究所だった。このソークがトドメを刺したと言っていい。その凛とした佇まい。海に向かってのびる水路を持つ空に開かれた庭。それらのどれもが、美術館だから、学校だから、研究所だからすばらしいのではなく、その建築そのもののあり方が素晴らしいのだ。ソークが仮に明日から別の機能の建物になっても、その佇まいが保持される限り、そのすばらしさは変わらないだろう。パルテノンが、パンテオンが、感動的なことと同じだ。建築はかくあらねばならない。開かれようが閉じられようが、設計のプロセスが市民参加型であろうがなかろうが、ソーラーパネルがついたりしていようがいまいが、建築的価値はそんなところにはない。
旅から戻るとすぐに原広司先生から、竹山にとってアメリカ建築のベストワンはどれだ、と問われた。一連のカーンの建築、特にソークでした、と答えると、そうか、俺はジョンソンワックスだったな、ライトの、と語りはじめた。
そう、ここでも、客観的なランキングを言っているのでなく、あなたにとって、ひいては自分にとって、最も惹かれた建築はどれか、ということを問うている。この姿勢、態度、こうしたことどもを通じて、私はヒトとしての原広司に惹かれていった。その志の高さや構想の射程の長さ、そして建築家としての矜持のようなものに。
あるとき、これはこの春GA JAPANに寄せた原広司追悼の文章にも書いたことだが、原広司先生は「建築に魅せられていた」と語ったのだ。それは生き方にも、日々のちょっとした振る舞いにも、そしてもちろん設計する建築にもその気配は満ち満ちていた。原研究室自体がそういう人たちの集合体だったのだ。麻雀をしていても、酒を飲んでいても、話はいつも広い意味での建築について、だった。
人間には個人の持って生まれた性格や資質というものがあるだろう。いくらトレーニングをしたって誰もが大谷翔平になれるわけではない。ただ、才能は大なり小なりその人間の置かれた環境によって育まれる。ヒトとの出会いやモノとの出会い、そして身の回りに起きた出来事によって、その時は意識していなかったにせよ、決定的な影響を受けたり、刺激を受けたりすることがある。そうしたコトも含めて、人は変化し成長していく。
建築に出会っても、惹かれない人ももちろんいる。かえって反感を持ってしまう人だっているかもしれない。私がこのように書き連ねてきた言葉も、そうした人たちにとってはまったく心に響かず自己満足に過ぎないと捉えられるかもしれない。当然である。惹かれる、というのは極めて個人的な事柄なのだから。あなたにとって、自分にとって、どうなのか、という位相の話なのだから。
多くの建築物は、そうした建築に惹かれた人たちによって設計されている。と少なくとも私は考えている。考えたいとも思っている。建築の可能性を個人として考えながら、それらが多くの他者に共有されることを夢見ながら。
なぜなら建築は、建築という行為は、そしてそれを通して実現される建築物は、多くの人々の目に触れ、都市や風景を形成し、共有されるものだからだ。自分はこんなことをやりたいのだ、と排泄物を垂れ流すような建築をつくられれば皆が迷惑する。そうした倫理的な側面をも含めて、私はずっと建築に惹かれてきたし、いまなお惹かれ続けている。日々発見があり、学びがある。
建築的瞬間の訪れ
人生で出会えることなどたかが知れている。その中で、惹かれるものに出会えた人生は幸いであるというべきだろう。惹かれるためにはつねにイオンの状態に身を置いておく必要がある。つまり反応しやすい状態に。しなやかな心で流れに身を任せ、なお流れの中で大切なものを見定める。いつもいつも意識的であったり反省的であったりすることは難しいだろう。ときに立ち止まり、そして流されるときは流されてみる。そうした心的なスタンスが、惹かれるという状態を生み、惹かれるという状態が、ことによると人生の中で大切なモノ・コト・ヒトを連れてきてくれるかも知れない。出会わせてくれるかも知れない。そのとき、その瞬間を見逃さないように。建築的瞬間(traverse7「建築的瞬間の訪れ」参照)もまた、そのようにして訪れるのだから。
竹山 聖(たけやま・せい)
建築家。京都大学名誉教授。作品に箱根強羅花壇、大阪府立北野高校、べにや無何有、新宿瑠璃光院白蓮華堂、双恵幼稚園、著書に『庭 / のびやかな建築の思考』(A+F BOOKS)、『京大建築 学びの革命』( 集英社インターナショナル ) など。「未完結な事物」、「天と地の対位法」といったテーマを通して建築的思考の可能性を追っている。