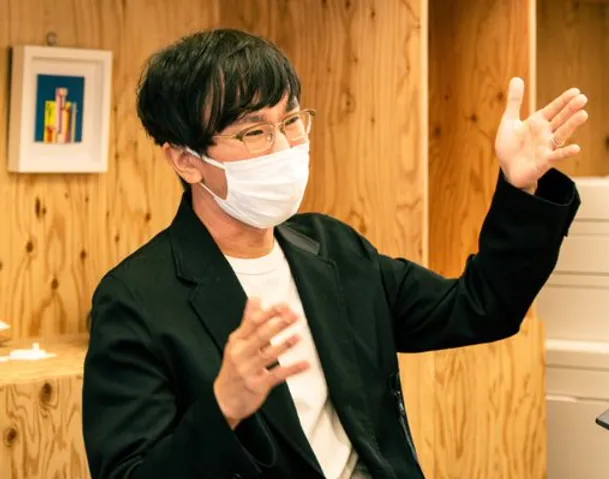
建築家/平野利樹|虚構と現実の境界を見る
自身の思想と境界
ーー平野さんの制作活動に境界が大きく関わっているとのことですが、具体的にどのような思想と関わっていますか。
境界論というと、いろいろな人に繋がりますね。プリンストン大学の後、東大の隈研吾研究室の博士課程に入ったのですが、隈さん自身も境界ということについて論じています。それは隈さんの師匠である原広司さんの影響があると思います。原さんの場合は集落論などの中で境界論をかなり書いています。原さんの場合だと、集落における境界にいろいろな穴が開いて、そこでどういった情報や物、物質が行き来するのかを論じています。有孔体理論も境界論ですね。一方、隈さんの場合「エンクロージャー」などのキーワードを使いながら、より具体的な設計論に展開しています。建築は必ず境界というものを作る必要があり、外側から内部空間を区切る必要があります。ただ、それを完全に箱として閉じるのではなくて、常に外部と何か連続性、繋がっているべきだという風に隈さんはいっています。境界は作らないといけない。しかし、なるべく存在感をなくして、空間が繋がっていくような形にしたい。そこで隈さんの場合、境界を粒子的なものとして作っていくということをするわけです。つまり境界のこちら側と向こう側がどのように繋がっていけるのかが隈さんの関心としてあるんですね。
一方で私の場合、同じく境界には関心があるのですが、ベクトルが逆です。隈さん達が活躍し始めた90年代はグローバリズムで次々といろいろな境界が消失して繋がっていった時代でした。インターネットによって地理的な制約を超えて人がコミュニケーションを取れるようになり、EUの発足によって国境という境界が限りなく薄くなり、ヒト・モノ・カネが自由に行き来するような時代になったわけです。ベルリンの壁の崩壊にみられるように、強く壁としてあった境界が、どんどん薄くなり、リテラルに壁・境界が崩れていきました。それに対して、今の時代の雰囲気として、むしろ消えつつあった境界が顕在化してきていると考えています。境界を消す方向で考えていくような建築のあり方ではなくて、 それとはまた別のベクトルで考えていくべきだと思い始めました。
これに関連して私が関心のあることの1つとして「穴」というものがあります。穴というのは境界に発生する状態です。原広司さんの場合だと、さっき話した有孔体理論で穴について語っていますが、空気や人の出入り口として行き来するような繋がるための穴というのが彼の中でのテーマになっています。私の場合、繋がっているけれどもその向こう側に何があるかわからない境界的な、切断されているようなものとして穴を捉えています。そういうところが境界と自分の建築のベースとなる思想の関係だと思います。

「Ontology of Holes」(Malformed Objects展)
ーー穴とデジタルが平野さんの制作活動の中心となっていると思いますが、デジタルに興味を持ったきっかけ、時期をお聞きしたいです。
私自身は小さい頃からコンピューターに慣れ親しんでいて、家にあったPower Macで絵を描いたりしていました。3DCGは高校生の頃に興味を持ってやり始めました。大学二回生の最初の設計課題では、皆手描きで図面を描くところを自分だけCGで描いていました。
デジタルは、留学する1つのモチベーションでもあったのかなと思います。当時、コンピュテーショナルデザインやパラメトリックデザインという言葉はなく、アルゴリズミックデザインと呼ばれていました。コスタス・テルジディスのアルゴリズミック・アーキテクチュアの日本語版が出たばかりの頃ですね。 RhinocerosやGrasshopperを使っている人も周りにはいなくて、パラメトリックな造形方法がない状況でした。一方で海外を見ると、いろいろなことが起こっていました。
ーー平野さんの制作活動の上で参考にしているものはなんでしょうか。
高松先生のシンプリシティの話をしましたが、一方で高松先生の作品を見ると、例えばキリンプラザやシンタックスなどのバブル時代につくられたものは、過剰なまでに装飾がされています。そのようなポストモダニズムの建築における過剰性にとても興味があります。私が学生だった頃は、ポストモダニズムは基本的には悪いものだという風潮がありました。ただ、プリンストン大学はロバート・ヴェンチューリ、マイケル・グレイヴス、チャールズ・ムーアなどの、ポストモダニズムの重要な人物が多く関係していて、留学当時はアメリカでもポストモダニズムを見直す動きが出てきた時期でした。その頃からポストモダニズムアレルギーのようなものが抜けてきて、一周回って面白いのではないかとなってきたと思います。
デジタルとフィジカルという境界を行き来することによってこそ出てくる表現の質
ーーロンドンのビエンナーレのインスタレーションをやって分かったことはありますか。
インスタレーションでは、コラージュというポストモダニズムにおいて使われていた設計手法をもう一度見直すことが一つのテーマでした。コラージュはポストモダニズムにおいて多用されていた手法ですが、その後あまり使われなくなりました。コラージュは異質なもの同士がぐちゃぐちゃと重なるため、多くの境界が発生してしまいます。先ほどの話とも繋がりますが、境界を消すという方向にトレンドが移行し、コラージュのような手法は時代に合わなくなりました。境界なく一つの連続するような空間を作っていくことが主流となる中で、コラージュは忘れられていきました。しかし、また境界が顕在化し始め、さらにポストモダニズムから時間が経ってアレルギーが抜けてきたこともあり、コラージュという手法にまた目を向けるべきだと思いました。しかし、当時のコラージュをそのまま繰り返すのではなく、デジタルテクノロジーを使うとどうなるのだろうと考えました。
ポストモダニズムにおいて、コラージュをするための要素は、常に抽象化、記号化されていました。しかし、デジタルテクノロジーを使えば、抽象化のプロセスを経ずに、モノそのものを膨大な情報として取り出して、それをそのまま加工、さらにはプリントアウトすることができます。もちろん、「情報量の膨大さの美学」で議論しているように、一切抽象化をせずにモノそのものを取り扱うことはできないのですが…。
それで、3Dスキャンを使って東京とロンドンの都市を構成するいろいろなものを抽出し、コラージュしていくという手法に結びついてきました。これによって今まで見えてこなかった都市のイメージを物質化させようという取り組みでした。

「Reinventing Texture」プロジェクションの様子 (photo: Prudence Cuming)

「Reinventing Texture」(ロンドンデザインビエンナーレ日本展示)(photo: Prudence Cuming)
ーーデジタルが発展したことで、自分の作品をアウトプットする時に気を付けていることや、考えていること等はありますか。
よく模型写真を使います。ずっとデジタル上でモデリングをしているものをそのままCGレンダリングで出してしまうと、物足りないといつも感じてしまいます。そこで、一度模型としてフィジカルに出力する、つまりデジタル上にあったものを一度境界を飛び越えてフィジカルに持っていくという過程が必要だと考えています。デジタルとフィジカルという境界を行き来することによってこそ出てくる表現の質というものがあると信じています。
ーー逆にCG等が進化したことによって、それがデザインに与える影響はありますか。
CGがかなり進化して、素人目には竣工写真とレンダリングの見分けがつかなくなってきていて、行き着くところまで技術が発達してきているように感じています。個人的には写実的な表現としてのCGデジタル表現が発達してきたことにより、逆に竣工予想のためのCGレンダリングと実際にできたものの間に軋轢が生まれてしまっていると思います。そのため、単に写実的でない表現の仕方がここから発展してくると思います。建築の表現はその人の世界の見方を定義している面があります。だから、単純に写実的であることが良いのではなくて、どのように世界が見えるのかを、その表現の中で定義することが必要になってくると思います。そういう点で、表現がますます多様化していく状況が生まれつつあると感じています。
軽やかにアートと建築の境界を飛び越えながら論じていく
ーーアートと建築の境界は何だと思いますか。
東京ミッドタウンに展示している作品はアートのコンペに出したものですが、審査ではアートの文脈で議論が行われ、建築の領域で使われているボキャブラリーや論理展開との違いを改めて痛感しました。一方で、アートを引き合いに出しながら建築を論ずることは、1つの手法として確立されていると思います。古典的なところだと、コーリン・ロウの透明性の議論がありますね。そこでは、キュビズムのブラックとピカソの比較や、フェルナン・レジェなどの画家が出てきたりして、それを足がかりとして建築における透明性が考察されています。アートなどの他領域から越境するような形で建築を論じていく流れは日本では少ないように思います。青木淳さんなどは軽やかにアートと建築の境界を飛び越えながら論じていくということをしていますが。個人的にはそういったことをやっていきたいですね。

「六本木の肌理」(東京ミッドタウンアワード)

「六本木の肌理」







