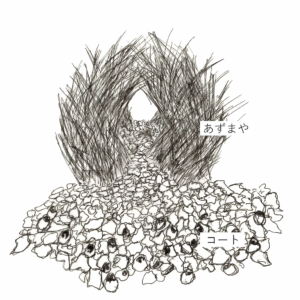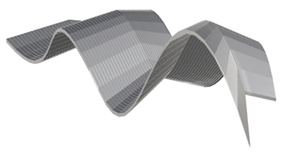道具を扱うことの本質|平田研究室 学部4回生 大山 亮
道具はまず、その仕組みや使い方という観点からみて素晴らしい。ある目的を達成すべく、いかに「つくる」かという知恵にわれわれ人間の知性が詰まっている。同時にそれは、人間がいかに世界を見て感じ、どのようにして向き合おうとしたのかを映し出している。道具を通じて身体感覚の中に生きる世界を落とし込んできたのである。道具を扱う行為の本質を見つめ直すことで、これからの世界をより豊かに生きる可能性を探ってみたい。
どう-ぐ【道具】
物を作り、また事を行うのに用いる器具の総称。 -広辞苑より引用
もう少し道具の概念を拡張させて考えてみよう。ある目的を達成するためにつくられる、あるいは使われる全ての物を道具と呼ぶことにする。本は情報を得るための道具であるし、紙は文字を書く/水を拭くための道具である。
― 快適さの罠
快適という言葉は、諸刃の剣ではないか。
あらゆる物事の善し悪しが快適さという指標で語られるようになった。合理性、利便性、安全性、経済性。あたかも完璧な正解があるかのように語られるその言葉に、私はまだなじめていない。快適さのゴールとは何か。暑い/寒いと感じた瞬間に空調が作動し、寒くもない暑くもない適当な湿度の空間が常に維持されている状態であろうか。仮に人間の向かう先がそこにあるのならば、我々は自らすすんで身体を退化させていくことになる。
現にほとんどの日本人は、空調が無いと生活できなくなった。「空調があるなら利用する」がいつの間にか「空調は無くてはならないもの」へと変わってしまった。エネルギーを投入して快適な環境をつくる→それに体が慣れる→エネルギーを使わないと体調不良になる→快適さを求めてますますエネルギーを使わないといけなくなる。身体を退化させてエネルギーを投入する、負のサイクルが既に出来上がっている。これだけの犠牲を払って、その引き換えに得られるものはたった一つ、快適さである。快適という言葉が諸刃の剣である理由は、快適さという指標から見ればより快適な状態を目指す以外に疑問を持ち込む余地が発生しないところにある。ひとたび快適さを求めれば、より快適であることを何の疑いもなく受け入れてしまう。快適さの罠である。
完璧を求めた外部化によってヒトのもつ力が失われている現象は、室内環境に限らず現代人の生き方において通じる部分が多い。
「(入浴時に全身に)石鹸をつけて洗うというのは、大便が毎日出ているのに浣腸しているようなものです。浣腸すれば全部丁寧に出るけれども、それを習慣として繰り返していると、浣腸しないと大便が出ないような体になることは御存じですね。それと同じように、いつも石鹸をつけて丁寧に(全身を)洗濯していると、皮膚の排泄するはたらきをすっかり鈍らせ、弱らせてしまう。自分の体のはたらきで掃除ができないようになり、汚れやすくなる。」 -野口晴哉 『風邪の効用』より引用
種無しブドウ、皮をむかなくてよいブドウ、といったものを最近よく見かける。何の疑いもなく手に取って食べているが、よく考えるとこれも快適さの塊である。ブドウを食べるだけの手間を本当に惜しんでいるのか。皮をむく経験をすることで、意外と実がひっついてくるあの感じを身体が覚えているし、上手にむけるむき方を自然と身につけているし…必要かと言われれば必要ではないかもしれないけれど、皮をむかない場合に比べて確実に自分のスキルは上がっているはずである。わざわざ取り立てて話すほどのことではないが、これもまさに身体スキルと快適さの交換現象である。
情報の快適さに関しても同様である。スマートフォンで検索すればたいていの情報は簡単に手に入れられるようになった。簡単に手に入れられるならば利用しない理由もない。あたかも自然ななりゆきで情報の快適さに飛び込んだ今、われわれの記憶力、判断力は確実に低下する一方である。スマートフォンを手放したとき、われわれの手元には何が残るのだろうか。
「そこまでして快適であることに価値があるのだろうか。」この問いに向き合う前に、一旦視点を変えて、道具の仕組みの側から人と道具の関係性について考えてみたい。
― 道具の連関
生きとし生けるものはすべて、外部世界(外部環境)に適応するかたちで存在している。生きるとは外部環境に対して内部の生存環境を変換し維持し続けることであり、その生存可能性に収束するかたちで生きる仕組みが形成される。(ⅰ)
道具を持たない生物にとっては、身体そのものが環境との媒体(-メディア-)である。[身体-環境]の連関が全てであり、生きてきた記憶は身体の仕組みの中に蓄積される。(ⅱ)
道具を使う生物は、[道具-身体]の連関をメディアとして環境を捉えている。すべてを身体の側で対応するのではなく、道具を「つかう」ことで生き方の幅を広げる。その結果、身体で適応する場合に比べて、はるかに短い時間ではるかに多様な仕事を生み出すことができる。 (ⅲ)
実在する世界とは別の観念上の世界を共有する能力を手に入れた人間は、[観念-道具]の連関のなかで道具を「つくる」ことを可能にした。物事が為るよりも前にその可能性の選択肢を広げ、選び取り、共有することができる。自らの意思で可能性を一つに限定する行為が「つくる」ということである。 (ⅳ)

「つくる」「つかう」という行為を通して、[観念-道具-身体]の連関を媒介として環境を変換するのが人間の選択した生きる術である。[観念-道具-身体-環境]この響き合いにこそ、人間の知性や感性、美しさというものが詰まっているにちがいない。
道具を持たない生物にとって、生きてきた記憶は身体の仕組みの中に結果として蓄積される。では、道具を扱う人間にとって、[観念-道具-身体-環境]の連関はどのような形で現れ残っていくのだろうか。一つには、それぞれの要素ごとに残されていく側面がある。道具は物体そのものの形として残されていくし、観念は文字や絵画、数式・理論の形で記されていく。二つ目は、各要素間の関係性の中に現れてくる側面である。身体と連動した道具を利用すると、道具を伴った身体技術として身体にそれが刻まれる。考えやイメージを表現しデザインを考えるうちに、道具を媒体とした観念と身体の結びつきが強化される。
ある目的を達成するために我々は道具を扱うわけであるが、そのプロセスを経験することは目的の達成以上に自分自身を成長させる働きをもたらす。道具の存在によって、人間は環境と向き合うスキルを更新し続けることが可能になったのである。どれほど些細なことであれ、人間にとって道具と関わる過程そのものが何より人間を人間たらしめている。日々この連関の中で自分自身を響かせることが、人間にとっての生きがいであり、生きる意味ではないだろうか。道具を扱うことは、もはや生きることそのものなのである。
― 快適さを超えられるか
快適であることに価値はあるのだろうか。再びこの問いに立ち戻ってみよう。よりよく生きようとする姿勢は生物としても人間としてのあり方とも一致するように思える。快適さそのものは変わらない欲求なのだろうか。より確かに生き抜くための方法として快適さが重要視されていると仮定するならば、どこかで度を越えたタイミングがあると考えられる。
一つ目のターニングポイントは産業革命である。動力を手に入れたことで莫大なエネルギーを扱えるようになった。それによって快適さに3つの変化があらわれる。最初の変化は、快適さそのものに対する考え方の変化である。「そこにある環境を手入れして快適さを生み出す」から「自ら管理し快適さをつくりだす」へと目指すところが変わっていった。道具から機械への移行である。二つ目の変化は、産業化による手間の省略である。物事の結果が何よりも求められるようになり、過程をなるべく省いた合理性が快適さとして認識されるようになった。三つ目は、資本主義の発展に伴う快適さの商品化である。より快適であるということが顧客にとっての比較項目となり、結果として見える形で快適さがはかられるようになった。
二つ目のターニングポイントは、高度経済成長期以降である。そもそも人間は進化の過程において、快楽を得ることで極限の環境を生き延びてきた歴史がある。生きる意味を見出せるからこそ人間は生きてこられたのである。しかし経済成長以降、飢えという脅威に対する外圧が一気になくなったとたんに、その快楽のみを貪るようになった。しなくても生きていける楽をするようになったのである。いってしまえばそれは、必要のない快適さである。「快適」という言葉が、生きるという切実さとはかけ離れたニュアンスをもつようになってしまったのもそのためである。
さて、こうしてすっかり世界にはびこった快適さの罠であるが、人間の進む自然ななりゆきの道なのだからとこのまま放置しておいてよいのだろうか。快適さの罠であげたようなある種の問題提起は、[道具-身体]の連関を絶つことの是非を意味している。連関を絶つことで、万人に共通して安定した手間のない快適さを提供できる。楽に生きるために自らの身体を犠牲にする。この生き方は、はじめに述べた道具を扱うヒトの定義とは全く違ったものである。[観念-道具-身体-環境]の響き合いは打ち砕かれ、道具を扱う過程こそが生きがいであるという人間最大の特徴を失ってしまっているのだ。我々に残された道は二つしかない。改めて生き方を見直すことでヒトとして蘇るか、完全に別の種であるヒト’(ⅴ)として新たな生き方の可能性に収束するか。二つに一つである。
どちらを選ぶか、私は前者を選びたい。なぜなら、人間自身の身体と精神は昔からそれほど大きくは変わっていないからである。ヒトを滅ぼすのは、ウイルスや他の生物ではなく、ヒトの生き方なのかもしれない。快適さなど、もはや幻想にすぎないとは考えられないだろうか。タバコを吸えば気持ち良くなるのと同じように、害があってもやめられなくなる。気持ち良くなるためには、より強く求め続けるしかなくなる。度を超えて自らを滅ぼす前に抜け出さないといけないのかもしれない。自分自身も、快適さの罠にすでに捉えられた一人である。簡単に変えられるものではないだろうが、このまま突き進むのを見ているだけにはなりたくない。
快適さに代わって人々を導くことができるものとは一体何か。道具を扱う連関の響き合いの中で、自分自身を輝かせる素晴らしさをいかに実現していくか、そこに勝負がかかっている。生き延びるためではなく、生き生きと生きるために道具と向き合う。快適さに対抗する最後の砦として、「生きる」に直結する道具としての建築にこだわり続けていきたい。
― 道具を扱うことの本質
道具を扱うことは、もはや生きることそのものである。
道具を扱うことで、生きる喜びを得ることができる。
それゆえに、ヒトは生き続けることができる。

撮影日 2021.03.10