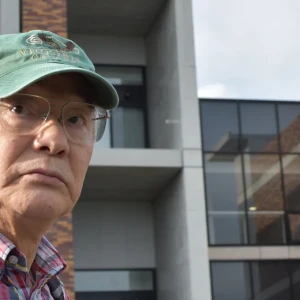【平田研究室】プラスチック爆弾は「生きられた公共建築」の夢を見るか?/Talk about 桂新広場プロジェクト
プラスチック爆弾は「生きられた公共建築」の夢を見るか?
平田研究室博士後期課程 大須賀嵩幸
生命がみずからの自由に形を与えるのは、すなわち生命が純粋な遺伝子決定論から離れるのは、ただ爆発物をつくることによってのみである。
カトリーヌ・マラブー
― 生きられた公共建築
平田研究室にいること5年、最近ようやく、自分が目指したい建築が何なのか、少し言葉にできそうな気がしている。それはたぶん、「生きられた公共建築」なのだと思う。
使い手の経験が空間の質に同化した「生きられた空間」は、しばしば家をモチーフに語られてきた。「生きられた家」では家族という単一の主体が空間と密に結びつき、特定の使い手による空間への関わりが空間に違いを生み出すからだ。より大きな規模の建築において主体が多数になると、家でみたような主体と空間との一体化は困難になる。特に、建築の所有者と使い手が一致しない公共建築においては、不特定多数の使い手は普遍化、最大公約数化されてプログラムに組み込まれ、建築空間に翻訳される。そうして、生き生きと使われることから遠ざかっていく。
この「生きられた公共建築」という矛盾をはらんだ理想に近づくためには、生きられた質と多数性を架橋する手立てが必要だ。SNSで人々が共感し合い、VRやARで今ここにない空間さえ体験できるいま、さまざまな思いが渦巻く状況から建築を立ち上げていくことが現実味を帯びつつある。そのとき建築をつくることは、建築家によるリジッドな個性の表現や、言われるがまま何にでも変化するような柔軟性(フレキシビリティ)とは違う、別の様相を帯びてくるのではないだろうか。
― 可塑性の可能性
脳化学の分野で注目される、可塑性(プラスティシティ)という概念がある。脳の可塑性とは、脳の神経細胞(ニューロン)をつなぐ接合部(シナプス)が個人の経験をもとにその伝達効率を変化させる性質のことだ1。ここには可塑性の、「かたちを受け取る能力」と「かたちを与える能力」の相異なる2つの性質が含まれている。「粘土には可塑性がある」という時は「かたちを受け取る」ほうの意味で、塑造や造形芸術(l’art plastique)のような人が造形するというのは「かたちを与える」ほうの意味である。前者の例で可塑性は硬直性と対置され、後者では可塑性は柔軟性とも異なることが分かる。あるいは、可塑性はリジッドとフレキシブル、つくり手と使い手の間を行き来する、時間を内包した概念ともいえるだろう。

図1 ニューロンをつなぐシナプス
脳の可塑性によって形作られる私たちの脳は、私たちによって生きられた脳である。その脳のつくり手は、ほかでもない私たちだ (私たちはそれに気づいていないかもしれないが)。同じように建築の、かたちを受け取り・与えるインタラクティブなプロセスを考えることで、可塑性を生きられた質と結びついた製作の概念として考えてみたい。
1 脳の可塑性は発達、調節、修復の3つのレベルで作用するという。
カトリーヌ・マラブー:わたしたちの脳をどうするか ニューロサイエンスとグローバル資本主義, 桑田光平ら(訳), 春秋社, 2005
― かたちを爆発させる

図2 生きられた公共建築
以上の仮説は、デリダのもとで博士論文を書き上げ、可塑性の概念をもってヘーゲルやハイデガーを読解し、神経科学や精神分析学に接近していくフランスの哲学者カトリーヌ・マラブーの仕事に影響を受けたものである。マラブー曰く、可塑性には「かたちを受け取る能力」と「かたちを与える能力」に加え、もっとも強烈な第3の意味があるという。それは「プラスチック爆弾」が想起させる「かたちを爆発させる能力」、すなわちかたちの消滅である2。この性質によって、可塑性はかたちの創造と消滅の二極の間に位置することとなる。
アルツハイマー病や自閉症、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者は、脳損傷や心的外傷によって別人かのように人が変わってしまうことがある。破壊自体から別の形式が生まれるという否定的な意味での可塑性3は、神経科学や精神分析学でも避けられる対象である。しかし、連続性を切断するような破壊的な出来事を、2020年に私たちは経験した。新型コロナウィルスの感染拡大によってソーシャルディスタンスの概念が生まれ、すっかり変わってしまった世の中を生きるために、オンラインやリモートワークを取り入れた新しい生活様式が普及しつつある。
ほんとうに生きられた状態とは、かたちを受け取り・与える連続的なプロセスだけではなく、もっと予想外の偶発的なものに開かれていることではないだろうか。マラブーの爆発のメタファーは、あらかじめプログラムされている予定調和の変化ではないものを思わせる。かつて磯崎は建築の「切断」4について述べたが、それはあくまでかたちを受け取り・与える連続的なプロセスの上での出来事であった。ここではより直接的な、何かが消えてなくなる文字通りの「切断」をプラスチック爆弾を通して考えてみたい。
2 カトリーヌ・マラブー:ヘーゲルの未来−可塑性・時間性・弁証法, 西山雄二(訳), 未來社, 2005
なお、マラブーは「ヘーゲルの未来」においてすでに可塑性の破壊的な側面に言及しているが、より重点的に扱われるのは「新たなる傷つきし者」「偶発時の存在論」においてである。
3 カトリーヌ・マラブー:新たなる傷つきし者――現代の心的外傷を考える, 平野徹(訳), 河出書房新社, 2016
4 磯崎は図書館の設計において「建築が成長する」という機能上の要求に対し、時間的な各断面が常に次の段階に移行するプロセスと考える「プロセス・プランニング」の方法論を提示した。条件に応じて流動的に実態を変化させていくプロセスをある時点で「切断」することによって、建築が具現化されるという視点が示されている。
磯崎新:空間へ, 美術出版社, 1971
またエリー・デューリングは、現代アートが無限的なプロセスを重視していると批判した上で、オブジェとプロジェクトの間にまたがる形態としての「プロトタイプ」という概念を提唱している 。
プロトタイプはプロセスの切断において現れる予期的なオブジェであり、プロセスを無限に開くことよりもプロジェクトに可読性を与えることが重要だという。
エリー・デューリング:プロトタイプ 芸術作品の新たな身分, 武田宙也(訳), 現代思想vol.43-1〈特集〉現代思想の新展開2015 思弁的実在論と新しい唯物論, pp.177-199, 青土社, 2014
― あの案があったから

図3 「北大路ハウス」の設計プロセスにおける、案の関係
実は「可塑性」という概念そのものも、実際に建築の設計を通して浮かび上がり、少しずつ言葉になってきたところがある。traverse17で紹介した「北大路ハウス」の設計プロセスでは使い手とつくり手がどちらも建築学生という理想的状態のもと、かたちを与え・受け取るプロセスが実現した。ワークショップや投票を経て、いくつかの設計案から段々状に連なる大空間が特徴的な「ふろしき案」を選び取ったのだが、この形態が「日常・講演会・展覧会の複数モードをもつ空間」という設計の指針となる概念を生み出し、その後のワークショップでは複数モードからの検討によってふろしき案の形状を具体的に決めていった5。
しかし、「北大路」の体験からは別の可能性も示唆されていた。設計の初期段階でふろしき案と同時に検討していた他の2案が、1案に決まった後の議論において浮かび上がってきたのだ。選ばれなかった案を通して考えたことが、具体的な平面プランや、素材の表現を決める手がかりになっている。それが可能だったのは、研究室メンバーと、継続的にワークショップに参加してくれた学生の間で密に議論が共有され、なくなった案のことを覚えていたからである。
建築を設計する際の案が生まれては消えていく過程に、可塑性の2つの意味を重ねてみる。1つは案が連続的に成長していく連続的な可塑性であり、もう1つは特定の案があったからこそ考えたことが、その案のかたちが消えても残るような、断絶的な可塑性である6。
5 大須賀嵩幸:つくる・すむ・ひらく「北大路ハウス」 京都の建築学生による新しい公共建築の実験, 新建築社, 2020
6 「偶発事の存在論」では「構築的な可塑性」と「破壊的な可塑性」という2分類がされている。
カトリーヌ・マラブー:偶発事の存在論 破壊的可塑性についての試論, 鈴木智之(訳), 法政大学出版局, 2020
― 桂新広場プロジェクト

図4 「桂新広場プロジェクト」のポスター
「北大路」は設計対象があくまで家(公共性の高いシェアハウスではあるが)であり、「生きられた建築」を考えることが比較的スムーズに行なえた。不特定多数の人に使われる公共建築や屋外空間においても、「可塑性」の概念を手がかりとして、「生きられた公共建築」をつくれないだろうか。
これから紹介する「桂新広場プロジェクト(仮)」は、京都大学のキャンパスの空き地に、学生の活動が見えるような屋外空間をつくる計画である。
計画地となる桂キャンパスは、京都市の中心部から離れた桂坂の中腹、高低差20mの敷地に位置する。大学院生を中心に全体で1500人ほどの学生が所属しているが、学生は研究室にこもりがちで、キャンパスで学生の活動を見かけることは滅多にない。このような状況に最初に異を唱えたのが、竹山先生と竹山研究室である。竹山研究室は桂キャンパスを対象として設計課題に取り組み、2018年度の「驚きと喜びの場の構想」は食堂に展示され、大きな反響を呼んだ。
竹山研の学生ののびやかな発想が工学研究科長・大嶋正裕先生の目に留まり、今回のプロジェクトにつながっていく。2019年の夏、大嶋先生から平田先生に「図書館と食堂の間にある空き地の利活用を考えてほしい」という話があり、平田研究室を中心に集まった有志の建築学生によって広場の設計がスタートした。
― つくることの狼煙を上げる






図5 6案の展示ポスター
広場の敷地は新しくできた桂図書館(2020年4月開館、デザイン監修:岸和郎)の横だが、桂の学生は建設中の建物が図書館だとは知らなかったりもする。その横の空き地に広場をつくるにあたって、まずはほとんど何のイメージもないような場所に建築の素案を立ち上げる必要があった。そこで私たちは、特徴的な形態の6案をつくり、展示を通してキャンパス利用者の意見を集めることにした。斜に構えがちな京大生(僕なんかも特にそう)の声を聞くには、知らないところで勝手に進んでいるような不信感を与えてはまずい。いっそ、あり得る様々な可能性をなるべく多く提示して反応をみようと考えた。
6案のスタディはそれぞれのキャラクターが出るように、3系統に分けて進められた。細長い敷地に対して、さらに細長い形を折りたたみながら配置していく「道」系統の2案(A,B)。対照的に、水平的な広がりをもった屋根やスラブで場所をつくる「屋根」系統の2案(C,D)。敷地を目一杯使う他の系統に対し、局所的に高さのある象徴的な構築物を立ち上げる「オブジェクト」系統の2案(E,F)である。
― 形にからまる意見

図6 展示の意見をシーンに翻訳する
6案の模型とパネルを展示して案への投票や自由記述のコメントを募り、キャンパス利用者の意見を11個の概念として抽出した。以下、概念を【】、元データからの引用を[]で表し、いくつかの概念を紹介する。
展示した6案の具体的な形に対し、はっきりと賛否を示す意見が多くみられた。E,F案の展望テラスやA,B案の高いところを通る道といった【空に近い場所】への期待は、坂の上に立地する桂キャンパスのポテンシャルを引き出すものである。A,C,D案のように地上レベルには柱だけが立ち現れるような【透明で見渡せる空間】が好意的に捉えられ、壁で場所を区切っていくB案には[もうちょっと穴が空いていたらよさそう!]との意見が寄せられた。
場所のイメージに関する意見としては、どこか別の場所で[のんびり研究や勉強ができる]【研究室からの逃げ場(アジール)】を求める声や、学部時代の市街地での生活を回顧する【吉田ノスタルジー】などがあった。
投票の結果は、浮かんだバスケットコートが特徴的なD案に多くの票が集まり、反対に建築によって場所を囲いとるようなA,B案は少数派となった。展示のねらいはここをどんな場所にしたいかという思いを集めることであり、投票で1位の案をつくることではない。そこで次のフェーズでは、先の6案とはパラレルでありながら、展示で得られた意見とどこかで結びついた案を、模型やパネルとは別の想像力を働かせる仕方で提示することが求められた。
― 地面のしつらえを整える

図7 地面整備案のスタディ模型
私たちが選択した次の一手は、地面のしつらえを中心とした敷地の先行整備である。この場所を実際に使えるようにし、具体的に場所を体験して広場のイメージをつくり上げていくことを考えた。
提案のベースとして、土を盛り掘りしておおらかに敷地を分ける地形を作り、その上に活動の手がかりとなる要素をちりばめていった。
図書館側のすり鉢状に囲まれた低地には日陰ができ、本を読んだり、屋外でゼミをするのにちょうどいい。ここにはさまざまな人数で【多目的な使い方】ができるように、動かせる家具を並べている。
一段上がった平場には【ちょっとしたエクササイズ】のきっかけとして、可動式のバスケットゴールと、健康器具を用意した。白く抽象的な形をしたこれらの器具には、広場の開放性を示すモニュメントとしての意味も込めている。キャンパスのあちこちに転がっていた木製キューブも白塗りすることで広場の要素に取り込み、サイン看板としても利用した。
もう一つ特徴的なデザイン要素として、地面に打たれたカラフルなコート鋲がある。展示で関心が集まりやすかった【記号的な地面の表現】を再解釈し、バスケットコートのフリースローサークルや3ポイントライン、あるいは家具を並べる手がかりとなるような補助線を地面に引いた。プロムナードから見下ろすと、このラインが全て円弧であることがわかるのだが、単純な幾何学図形を用いて恣意的になり過ぎないデザインを試みた。
― 断絶的な可塑性
このプロジェクトにおいて「可塑性」の概念が試されたのは、6案から地面整備案への移行においてである。案の形式としては「断絶」しているのだが、6案がなければこの地面整備案は生まれなかっただろう。6案の展示から得たキャンパス利用者の思いの断片を建築的要素に翻訳し、それらを重ね合わせるようにして今回の地面整備案がつくられている。
9月にはついに広場がオープンした。特にバスケットゴールが人気で、京大生はもちろん、地域の小学生も遊びに来てくれているようだ。土でできた広場は足跡やボールで踏み固められ、あるいは雨風で地形の角がとれて、少しずつ表情が変わってきた(そういう意味でも可塑的な広場である)。広場がどこまでそれに近づけたのかはわからないが、「生きられた質」を持って設計された空間は、実際に生きられる段階へとスムーズに移行するのだろう。
今後は、広場でのイベント企画や屋台などの什器設計も構想している。さまざまな人が広場に足を踏み入れ、思いを馳せたことを取り込んでいった先に、最終的にこの広場に6案のように元気な建築が立ち上がるのか、あるいはまったく別の何かになるのか。これは桂キャンパスの仲間たちと育てていく建築なのである。

図8 地域住民に利用されている広場の様子