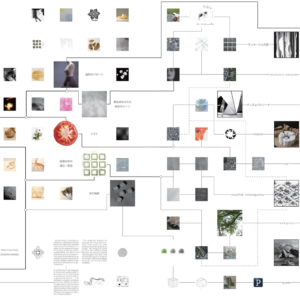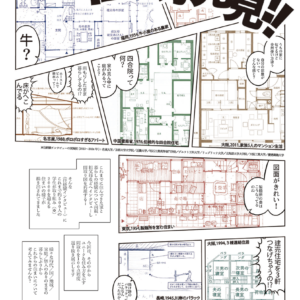【小見山研究室】境界線上で実寸大の物質性と戯れる
Ki-time
著者:野村祐司
林浩平
Ki-Timeパヴィリオン
次に紹介するKi-Timeは2021年7月に始まり2022年8月の施工まで1年余りにわたって開催されたフランス・ベトナム・日本の学生・建築家たちによる国際ワークショップである。アンスティチュ・フランセ関西(在京都フランス総領事館)とヴィラ九条山を敷地に2つのインスタレーションが制作された。小見山研究室は四回生を除くフルメンバーで参加し、主に日本人学生たちが前者に、留学生たちが後者に参加することとなった。日本の学生たちがリードして図面化していく時の精密さ、フランスの学生たちがリードしてそれを物質化していく時のスピード感が印象的であった。特に小見山は前者のプロジェクトに担当インストラクターとして参加した。それは在京都フランス総領事館の中庭に点在する歴史の痕跡へ訪れた人を誘う4つのゲートである。PPテープで縫い付けた合板を、3Dプリント部材で角度を拘束し、結束バンドで引き寄せ、2本の紐で張力を入れ固定している。実現にあたっては、小見山が普段協働している木造建築の関連企業にも材料提供として参加いただいた。針葉樹合板と広葉樹合板、ガラスコーティングと撥水加工。木の外部仕上法比較のため4つ全て異なる仕様にした暴露試験体でもあるのだ。これ自体が庭を新たな視点で体験するための小さな建築であると同時に、木造建築の未来に向けた実験の一部でもあるのだ。
アンスティチュ・フランセ
学生主体のパビリオン共同制作が数あるなかで、このプロジェクトを特徴づけるのは意匠と構造の協調といえるだろう。意匠が構造を要請し、構造が意匠に、予期せぬ自由を与えながら形を獲得した。この協調は、振り返れば、施工する学生側の技術的・時間的制約と、管理・運営側の要求する性能がもたらしたようだ。(図1)
その次第をたどる前に、このゲートを成り立たせている主な要素を3点、整理する。
① 全体の幾何:直角三角形の相似による長方形の分割
設置時に捻れが生じる。→a.ゲートの変形・倒壊に抵抗する、b.(視覚的複雑さ)/(加工の複雑さ)の比が大きい、c.折り畳みが可能である。
② 板の構成:合板+長手方向の支柱
開閉方向の力を支柱が負担するため、合板は特に地面付近において自由となる。→a.軽量、b.尾の追加が可能
③ 接合部:回転が制限されたピンと、3Dプリントしたジョイント
ゲートが閉じる方向にモーメントを加えると、テープの引張とジョイントの圧縮抗力が抵抗し、形状が定まる。→a.設置・撤収が容易、b.角度のバリエーションが作成可能、c.加工が容易

図1
~設計~
全ては「折り紙がリボンのように連続する」イメージ(図2)から始まったが、配置を模型で検討する際に、そのイメージを十分保持しながらも単純で大量に制作可能なユニットを考えた。それは図3のような短冊を折っただけのものに過ぎなかったが、5/14のWSではこのパターンをたたき台として、板の構成、接合部、接地の3点が議論された。

図2

図3
まず板の構成の議論では、モノリシックな板を理想としながら剛かつ軽量なものが目指されたため、中空の板をつくる案が複数生じた(図1-a)。また、接合部の議論は図1-bに示すような「剛orピン」と「角度の付け方」によって整理できるだろう。ピン接合の方法として金属蝶番のほかにテープによるヒンジも考案され、それが(どういうわけか)膜によるヒンジへと発展を見たところで、WSは終わる。
WS後、あらゆる案を検討したが、大きな進展があったのはヒンジ案だった。敷地では月に一度のマルシェがあり、設置期間には台風も予想されるといった条件から、少人数で簡単に設営、撤去可能な仕組みが必要だった。加えて、状況に応じた設置・撤去を考えるなら、保管方法も考える必要があった。そのようなことを考えながら構造模型を制作していた時に、ある事実を発見する。それは図4のような幾何(当初、ただ短冊に折り目を入れたに過ぎなかったもの)を用いれば、理論的には両端の操作で全体が持ち上げられること、更には、折りたたみさえもが可能だということだった。これによってヒンジ案は実現性を増す。スペーサーによる角度調整案を吸収し、板の構成をそれまでの中空のものから板+支柱へ合理化させた結果、新たな接合方法が考案された。施工性を向上させる案も盛りこまれ、接合部と板の構成についての主要アイデアが出そろう(図5)。続く6月には協賛・提供企業との協議を進めながら、モックアップに向けた細部の調整が進められた。

図4

図5
だが一つ、解決策の出てこない箇所があった。そもそもヒンジをどうつくるか、である。図4の模型が端的に表しているように、このユニットはゲート外側に張られた一枚の膜がヒンジとして働く設計だった。しかし、引張強度や繰り返しの曲げによる疲労、板へのつき方等を考えると現実的ではない。そのまま7/2モックアップ制作の日を迎え、簡単に成立するものとしてPPテープを仮採用(図6)し、数度のモックアップを重ね、施工へと向かう。(図7)

図6

図7
~施工~
施工は五条の宿や平岩という民宿の隣の作業場で行われ、ゲートを組み立てた後に現地に運び設置した。フランスチームはその宿に8/8から2週間滞在し、板の加工から立ち上げまで全てを12日間という短い期間で行うという過密スケジュールであった。8月、灼熱の太陽のもと、設計時には決めきれなかった詳細部分や問題点をここで解決しながら作業を進めていった。
英語でフランスチームとコミュニケーションをとりながら順調に進めていくなか、最初に立ちはだかった問題は構造的な強度であった。設計時には、足を剛接合で固定すればジョイントの圧縮抗力によって形状が定まる予定だったが、設置するアンスティチュの地面が想定よりも硬く、足をピン支点でしか固定できないことが分かったのだ。そこで、ペグを地面に差し、支柱に固定されたアングルとペグをピン接合するという接地方法をとり(図8)、ロープによる引張力で強度を保つことになった。この引張のためのロープをどこにどのように取り付けるかという議論がなされ、歩く際に邪魔にならず調整もしやすいという点、さらに元々のコンセプトに沿うようにデザイン面も考慮しながら、最終的に図9のように決定した。

図8

図9
次に問題となったのは、ゲートの設置場所である。当初、4機か5機つくる予定であったが、最終的に敷地には4機設置することになり、その配置をどうするか議論する必要があった。折り紙がリボンのように連続するというコンセプトをあらためて共有し、模型の上でフランス人たちと検討した結果、4機が地面を介して繋がっているように見えつつ、それぞれのゲートが場所の景色を切り取っているような配置が実現した。

図10
その他、膜をどこまで被せるか、ロープの結び方、結ぶ位置や種類などの詳細部を適宜話し合って決定した。また、板同士をPPテープのみで繋げているとゲートを組み立てる際に隙間が出来てしまうため、結束バンドで仮止めしたり、ペグを打つ位置によっては深く刺さらないため、打つ角度を試行錯誤するなど、その場に応じて柔軟に対応して施工を進め、8/20、無事竣工した。
2021年7月に始まったこのワークショップは、コロナもあってzoomでコンセプト・基本設計がなされ、施工が延期され、やっとのことで対面での施工が始まった。設計から施工まで、時期や期間の関係で人が抜けたり加わったりしながら進められてきたため、先にも書いたとおり、協調が非常に重要であった。制作するなかで、図面どおりにいかない難しさを実感しつつ、柔軟な対応やコミュニケーションの大切さ、自分たちの案が形になることの喜びを身をもって体感できる貴重な機会であった。