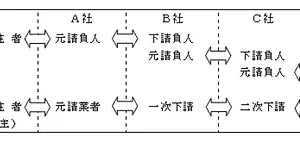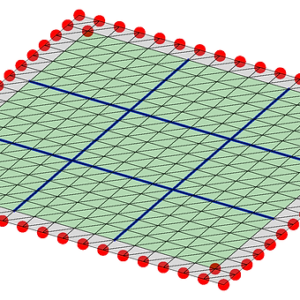述語面としての「仮面」建築|石井 一貴
― 述語面としての「仮面」
「仮面」と聞くと現代の感覚を持つ人にとっては何かネガティブな印象を受けるかもしれない。しかし、本来「仮面」というものは、「自己同一的な自我の上に蓋をするように隠すもの」という意味は持ち合わせてはいなかった。
哲学者の坂部恵は『仮面の解釈学』の中で、〈おもて〉(=仮面)についてこのように述べている。
〈おもて〉とは、〈主体〉でも〈主語〉でもなく、〈述語〉にほかならないのだ。
〈おもて〉のかたどりの統一とは、西田哲学の言い方をかりていえば、「主語となって述語とはならない」のではなく、反対に「述語となって主語とはならない」根源的な〈述語面〉のかたどりの統一である。(中略)述語は、具体的場面におかれ、ひとの口にのぼることによって、完全なものとして生きる。〈仮面〉もまたこのような〈述語〉にほかならない。
近代的自己同一性のもとに成り立つ主語面としての「仮面」は、何かを示すもの、である。その「仮面」と対面する人は、意識の中でその「仮面」との間に距離があり、完全な他者同士としてコミュニケーションを成立させる。
一方で述語面としての「仮面」は、先ほどの坂部恵の文章のように、単体では「欠落」をかかえた存在であり、人々の口にのぼることによってはじめて成立する。「仮面」はそれ単体として意味を含む記号ではなく、なにかしらのかたどりを持っているが、それは接する人々によって捉えられることで初めて成立するものである。その「仮面」は対面する人にとって、意識の中では時間的にも空間的にもゼロ距離であり、「今
=ここ」におけるあらわれとして、自己と他の境界を乗り越えるものである。そこでは「今=ここ」で行われていることが重要であり、それは様々な関係性の中に対面する人自身が置かれることにより、はじめて現象として見出されることであるといえる。
この捉え方は、自己同一的な存在を目指してきたモダニズム建築に対抗して生まれてきた建築にも、同じことがいえるのではないかと考えている。
― ヴェンチューリの「仮面の再発見」
「仮面」を持つ建築を考える中でまず思い浮かんだのが、ロバート・ヴェンチューリによる「デコレイテッド・シェッド」の概念である。
近代建築はその自己同一的な存在であることを追求した結果、都市へのあらわれを欠いた建築物となっているということを、ヴェンチューリは『ラスベガス』において指摘している。その反対にラスベガスの大きな看板が、都市を移動する人々に対してメッセージをもつものとしてあらわれていることを積極的に捉え、箱もの建築物に大きな看板が都市に向けて取り付けられたような建築のダイアグラムである「デコレイテッド・シェッド」を発表した。これはいわば、「ポシェ」をもつ建築物と同様に、都市に対しての表れ方の論理(「仮面」)をもつ。このダイアグラムによって建築はファサードを取り戻した。すなわちそれは「仮面」を取り付けたような建築であるといえるかもしれない。
しかしここでは、あくまでモチーフは看板である。それは一つの意味に読み込めるある種の記号であり、どちらかというと近代的な「仮面」と言えそうである。実際ヴェンチューリのいくつかの建築物や設計案の中には、そのように記号的でわかりやすいファサードをもつものがある。一方でヴェン
チューリは、述語面としての「仮面」建築もつくっている。例えばイェール大学数学教室のコンペ一等案においては、周囲の街並みとの調和を図るだけでなく、普段意識されることのないそれらを強調するように建築物をつくっている。ここでも内部空間の論理と外部の都市へ向けたファサード(立面)の論理を切り離して操作を行っているが、その時に単に周りの建築物を模倣するのではなく、少しエラーを起こしその文脈から脱臼を生じさせることで、周りの建築物を浮き立たせる効果を生んでいる。例えば東北側立面には、既存の街並みにはないような大開口が設けられ、そこに十字状の柱梁が入れられている。こうした周囲とのズレを演出することで、普段意識されない周囲の建築物が逆説的に浮かび上がってくるのである。また、周囲の建築物の” 部分としての建築” になるだけでなく、この建築はそういったエラー的な要素を持つことで、周囲の建築物との関係性の中で語られる。そこではじめてこの建築が完全体として” 全体性をもつ建築” としても成立することを意味するのである。これは、述語面としての「仮面」建築であるといえるのではないか。
― 飯田市美術館における「仮面」

飯田市美術館内観(レイヤー状のシーン構成)

飯田市美術館外観(正面のジグザグのガラス面)
原広司がつくる多くの建築も、僕は述語面としての「仮面」建築であると感じている。以前、原広司の故郷である飯田市を訪れたことがある。飯田市は南アルプスと中央アルプスという急峻で高い壁のような山に挟まれた、幅の狭い谷間に位置する。そのそそりたつ壁のような山は朝・昼・夕方・晩と一日の中でも太陽の角度によって表情が変化していく。山の存在感は圧倒的で、その表情の変化はそのまま飯田市の風景において大きな影響力を持っていた。そのため、山と平行にレイヤー状の風景としてのシーンが重なっているように感じた。
原広司は飯田市に美術館を設計している。この美術館は、まさにこの地形と同じように、大きな壁に挟まれた細長い谷のような建築物となっている。この細長い建築に対して、原広司は舞台幕のようにレイヤー状にシーンを並べている。つまり、建物の正面だけでなく内部にも同じように表情の異なる面がいくつか設けられている。短辺方向に移動すると、シーンのレイヤーを横断することになり、同じ建築の中で多くの表情を経験することになる。しかもこの横断は体験者によって思い思いになされる。これは、原広司が『ディスクリート・シティ』で語っている” エレクトロニクスの効果”、つまり様々な場面がヒエラルキーのない形で並置され、そこに人が興味のあるものについて瞬間的にスイッチングできる面白さを含んでいる。した
がって、この建築は来訪者によって様々に表情が読み取られ、読み替えられていく建築となっている。これは、面がはっきりとした形で並んでいることで、より分かりやすい形となって認識されることが大きな要因であると考えている。加えて、虔十公園林フォリストハウスでもなされているようなガラスの反射と透過のオーバーレイという試みはこの建築の重要な要素である。ここでは、一部のファサード面をジグザグのガラス面にすることで、内部からそれを一つの面として捉えた時に、先述のレイヤー状のシーンが散在して外の風景と重なって見えるようになる。また光景は観測者の動きの中で異なって見える。また、観測者の興味などによって焦点が変わることで、見えるものやシーンが異なってくる。この様々なシーンを含む反射と透過のオーバーレイ効果を持つガラス面は、その特徴的な形状であるギザギザ面が意識されることはない。そこに写る現象が問題となるのである。まさに述語面としての「仮面」建築を体現するための一つの要素であると考える。
このように、人々の心情などによって異なるようにあらわれる建築は、訪れる度に新しい発見を与えてくれる。また従来の機能的な建築のように、単に用意された世界を第三者として味わうのではなく、自分が主人公である一種のファンタジーの世界に誘われるような感覚にもさせてくれるように思う。こうした効果は、機能的で一義的なあらわれ方しかもたない建築には不可能である。
これらの試みが行われた少しあとの時代には、多くの場面で建築の記号性がクローズアップされることになった。しかしヴェンチューリや原広司の例のように、記号としてとらえることのできない〈おもて〉のあり方を想定することで生じる、建築の可能性について今後考えていきたい。
参考文献:
『仮面の解釈学』坂部恵(東京大学出版会)
『建築の多様性と対立性』ロバート・ヴェンチューリ 伊藤公文訳(鹿島出版会)
『ラスベガス』ロバート・ヴェンチューリ 石井和紘、伊藤公文訳(鹿島出版会)
『ディスクリート・シティ』原広司(TOTO 出版)