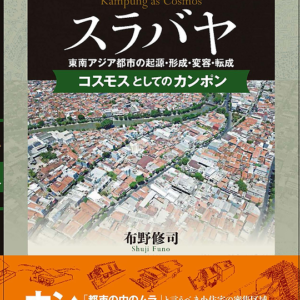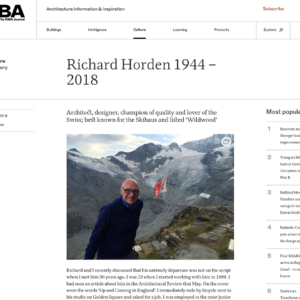コーラス/ コーラ、あるいは、形なき形をめぐって|竹山聖
・・ ・・
― なるものとあるものを結ぶもの
プラトンによれば、宇宙という万有を構築しはじめるにあたって、神は火と土を用いた。
しかし二つのものを結び合わせるのにはどうしても第三のものがいる。二つだけではうまく結び合わさることはできない。「一種の絆のようなものがその両者の中間にあって、それらを結合させるものになってくれなければならない」※7 。二項対立の教祖のようなプラトンは、第三項の導入が嫌いではないようだ。のちに論ずる「コーラ」もまた、そのような第三項である。
それではその絆とは何か。「その本性上、最も見事にやってのけるのが、比例というものなのです」※8 と、プラトンは断定する。二つのものを結び合わせるのは「比例」※9 である、なるほど。
ところがプラトンは宇宙が二次元でなく三次元の立体であることから、この第三項が単数ではなく複数でなければならない、つまり比例に二要素が必要だ、として、なんと水と空気をあげるのである。プラトンは数学者というより詩人である。比例にもメタファーが必要なのだ。プラトンの言説はそもそもメタファーに満ちている。ジャック・デリダが、その著『コーラ』の原註において、ある種のプラトン主義的伝統として「メタファーとは叡智的な意味に接近するための感性的な迂回である la métaphore est un détour sensible pour accéder à une sens intelligible」※10 と語っているほどだ。「まさにこのようなわけで、神は、火と土の中間に水と空気を置き、そして、それらが互いに、できるだけ比例するように仕上げました」というわけだ。「四つのもの(火、水、空気、土)を材料にして、この宇宙の身体は、比例を通じて整合されて生み出され、またそのところから親和力を得た」※11 のだった。宇宙は比例と親和力に満ちている。
ただその上で、回転する宇宙の物質相互の配置における比例の数的関係について言及することも忘れない。数学者の顔も見せるのである。
もちろん、ここで重要なのは、プラトンが哲学者か文学者か詩人か数学者かといったことではない(そのいずれでもである)。そうではなくて、関係項の導入、というその思考の方法である。観念と物質、形相と質料、などといったふうに、いつも二項対立に還元しきるわけではないのだ。
目に見える物質、すなわち「なる」ものたちの世界に「ある」が介入するにあたって、理性のとらえる秩序、それが「比例」であった。さらにそこに躍動をもたらすものとして「魂」という概念が導入される。これは生命力とも訳される言葉だ。※12 理性はこの魂の部分である、とされている。裏を返せば、「魂」を持つもの必ずしも「理性」を具えているとは言えない、ということだ。「魂」は「理性」からはみだしている。しかし「理性」は「魂」を基盤にしてはじめて成り立つ。※13 ここでプラトンが描き出しているのは、いわば、生命体としての宇宙論である。
プラトンは、宇宙の中心には魂=生命力とでもいうものがあって、これがあまねく行き渡って物体の配置と運動に美しい比例をもたらしている、と考えたのである。「このようにして生まれてきたもの(宇宙)が生きて動いていて、永遠なる神々の神殿となっている」※14と祝福もしている。
この永遠なるもの、というモデルに限りなく近い身体(天体)に、つまり宇宙に、なお欠けるものがあると感じて、その生みの父は「時間」を与える。生成した宇宙に、運動を与える。宇宙に夜と昼を、月と年を与えるのである。「宇宙を秩序づけるとともに、一のうちに静止している永遠を写して、数に即して動きながら永遠らしさを保つ、その似像」※15 を。
この「数に即して動く」というあたりが、やはり詩人かつ数学者であるプラトンの面目躍如といったところだ。数は比例である。比例は親和力である。万有をあまねく結び合わせる。ニュートンはプラトンに啓示を受けていたのかもしれない。
この宇宙が「永遠なる生きもの」※16 であるように、万有を結び合わせつつ運動をももたらす「時間」が、やはり不滅の永遠の相の下に導入される。物質は消滅を繰り返すが、時間は永遠である※17。「なる」ものが「ある」ものへと、結び合わされてゆく。
7 プラトン, 前掲書, 31C, p.35.
8 プラトン, 前掲書, 31C, pp.35-6.
9 プラトン, 前掲書, 32C 註4, p.37 によれば、プラトンは異質的なもの同志を結合させる要因として、エンペドクレスの説く「親和力」にあたるものを「比例」に求めた。
10 ジャック・デリダ ,『 コーラ:プラトンの場』,守中高明訳, 未来社, 2004, p.91.Jacques Derrida, Khôra, Galilée, 1993, p.99.
11 プラトン, 前掲書, 32C, p.36.
12 プラトン, 前掲書, 30B 註3, p.33.「魂」と訳した原語は、元来「生命」もしくは「生命力」とでも訳してよい語。
13 プラトン, 前掲書, 30B 註3, p.33.
14 プラトン, 前掲書, 37C, pp.46-7.
15 プラトン, 前掲書, 37D, p.47.
16 プラトン, 前掲書, 37D, p.47.
17 リュック・ベッソンの映画「LUCY / ルーシー」(2014)では、圧倒的知性によって時間が究極の存在と洞察される「落ち」がついている
― 理性と必然
プラトンは、やがてコーラという語を導入するのだが、その直前に、「理性」と「必然」という対語にも話題を向けている。
前にも引いたが、ティマイオスをしてプラトンがこう語らしめていたことを思い起こしてみよう。「話し手のわたしも、審査員のあなた方も、所詮は人間の性を持つものでしかないということ、従って、こうした問題については、ただ、ありそうな物語を受け入れるにとどめ、それ以上は何も求めないのがふさわしいのだということを思い起こし、何人にも劣らず、「ありそうな」言論をわれわれが与えることができるなら、それでよしとしなければなりません」※18 と。
理性的存在に一気に人間が到達できる、というふうにプラトンは話を進めない。むしろ逆であって、プラトンは人間の認識力、思考力に即して、徐々に理性的存在、叡智的なるものに近づこうとしている。それも、この世界の中にある、つまり目に見え、手に取れる物質世界の中にある、さまざまなものたちの在りようを眺めながら、これを認識する仕方、そしてこれをとらえる言論の質によって、そう、むしろ言論の質によって、プラトンは世界の認識のレベルを測っていくのである。
そこで理性を一気に叡智的存在に適用するのでなく、この世の中のさまざまな物体に、生成してきた物体に、適用する。はたしてそれが、「理性」を通じて製作されたものか、あるいは「必然」を通じて生じてきたものか、と※ 19。
「理性」と「必然」という区別の他に、つくられたか生じたか、という区別がここでなされていうことにも注目しておいてほしい。「理性」は意志に基づき、ものを「つくる」主体である。「必然」は自然に「なる」だけの客体である。が、まずは「理性」と「必然」である。
こちらに目を向けよう。
プラトンは、この宇宙の生成は「必然」と「理性」の結合から、その混成体として生み出された、と言う。しかも「理性」が「必然」を指導する役割を演じつつ※20。ここでの含みは、言うまでもなく、理性が善で、必然は彷徨、つまり混沌、ということだ。羊たちには羊飼いが必要、という発想である。この点、極東アジアの稲の生育を日々草取りしつつ見守る農耕民とは、やや発想が異なる。自然の叡智に期待する思考とは、異なっている。「ある」べきものを「つくる」、という思考と、「なる」ようにしかならない、という思考。自然を改革していく思想と、自然を修正していく思想。もちろん優劣を論じているのではない。
話を戻そう。付された註によれば、ここでいう「必然」を通じて生じるものとは「火・空気・水・土といった素材の世界のことを意味する」※21 のだという。ほうっておけばどこを彷徨っていくか知れぬ羊たちたる素材たち。意志を持たずあてもなく。混沌の体現者たち。
とするなら、現代の言葉に引っ掛け、「必然」はいわばエントロピーと理解してもいいかもしれない。単なる素材という物質世界に潜在する彷徨、無秩序への傾斜。つまり「理性」が秩序、「必然」がエントロピー、である。エントロピーは増大に向かう。火、水、空気、土、すなわち素材の世界の無秩序の状態は、どんどん拡散していく。
これがいかにして秩序づけられるのか。そこに宇宙のように秩序だった系が生み出されるのか。この説明にプラトンの夢が込められている。
プラトンは、この世界には、全体として、そもそも何らかの秩序へ向かう力が働いているのだ、と見なした。でなければかくも秩序だった宇宙が出来上がるはずがない。数的比例に満ちた、美しい、善なる世界が。
ただし現実を見てみよう。当時の古代ギリシアの話である。いくら語り説こうとも、プラトンのめざす理想の国家は遠い。師ソクラテスも毒を仰がされる始末だ。この世界の混沌にプラトンもまた嫌気がさしていたのではないか。だからこそ、プラトンは秩序への道筋をさまざまな形で示唆しようとした。イデア、それは理想世界である。しかしそこに一気に到達できるほど、物質世界はその混沌を脱していないし、人間は愚かさを脱しきれない。
イデアへの一気のワープが不可能であるなら、そこにひとつひとつ篩(フルイ)をかけて、少しずつ善きものを救い出して行かねばならない。第三項はそのようなプラトンの願いが込められた仮説であったのではないか。「比例」も、そしてフルイをそのメタファーのひとつとする「コーラ」もまた。
「理性」と「必然」の間に横たわる距離が、プラトンをして仮説的第三項の導入へと向かわしめた。羊飼いプラトンに、農耕民的自然の叡智―ゆっくり段階を追って物事の成熟を待つ思考の導入へと舵を切る―が介入し、その方途を探らせた。
『ティマイオス』において、イデアの似像である宇宙の生成を語る前半と、ミクロコスモスたる身体の構造を語る後半との間に差し挟まれた場所に、「コーラ」は位置づけられている。すなわち、「時間」の導入を語る文章、そして「理性」と「必然」を語る文章、さらに、あの謎に満ちた「コーラ」が、デリダを魅了した「コーラ」を語る文章が、差し挟まれている。これはどういうことか。
それはプラトンが、世界を理想のイデアと混沌の物質へと分割し、しかるのちに一気にイデアへの跳躍を果たす、という戦略からあえて距離を取ってみたということではないか。
「理性」と「必然」のアマルガムであるこの世界を、さまざまな混合比を持つグラデーションと見て、「時間」を待つという迂回の中から、さらには「自然」(そのような言葉がプラトンによって意図的に使われているわけではないが)の有する漸進的な作用の中から、ゆっくりと、段階的に、叡智的世界へ向かう、そのような戦略の可能性を暗示する気になったからではないか。
プラトンの世界観はそもそも、ものは秩序を希求する、という信念に導かれていた。いや、秩序を希求すべきである、という当為、善への志向に貫かれていた。そうした方向へと人間を導くのが理性であった。感性の対象=「なる」ものが、いかにして理性の対象=「ある」ものへと導かれていくのか、と。生成がいかにして有へ、存在へと向かっていくのか、と。そしてそれが可能なのか、と。人類の歴史は、秩序を希求する歴史に他ならない。そして秩序はすでに、「ある」。「ある」として、善のイデアとして、示されている。混沌たる世界は理想的な世界への改変を待ち受けている。
叡智的なものと感性的なもの、さらにいうなら、叡智的な言論=思考と感性的な言論(感覚)=思考という区別、その関係の考察を通して、人間はいかにしてより美しく善なる世界へと導かれうるのか、それこそがプラトンが問い続けた問いであり、求め続けた答えであった。
そして、この「なる」ものから「ある」ものへ、混沌から秩序へ、という運動をもたらす第三項を、プラトンはあえて導入し、それに名前を付ける。それが「コーラ」であった。時間をかけた自然の作用の中で、「必然」から「理性」への道筋を辿る、グラデーション、迂回、スクリーニング、プロセスへのまなざしが、そこに見て取れる。
18 プラトン, 前掲書, 29D, p.31.
19 プラトン, 前掲書, 47E, p.72. さて、これまで話して来たことは、少しばかり例外はありますが、ほかは「理性」を通じて「製作されたもの」を示して来たのです。しかしそれとともに「必然」を通じて「生じる」もののことも合わせて話さなければなりません。(かぎ括弧は筆者)
20 プラトン, 前掲書, 48A, p.72.
21 プラトン, 前掲書, p.73, 註2.