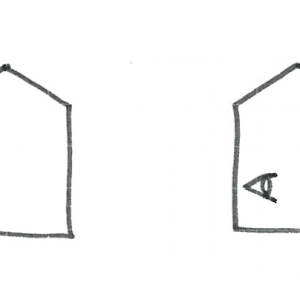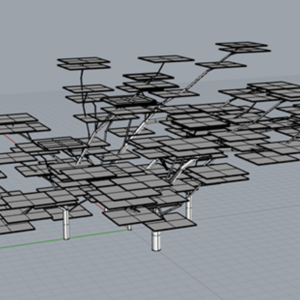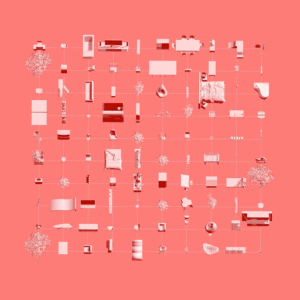ひとらしさを創造する周縁制御の原理|伊勢史郎
― はじめに
京都大学工学部建築学科・建築学専攻に就任した1998年からの15年間はとても刺激的で充実した教員生活を送ったが、特にこのトラバースに関わることより与えられたものは大きい。建築学という理系の知識を道具にしながらも、文系的なセンスで実践的に社会に関わる学問分野の先生方と触れ合うことができたことは極めて幸運だった。トラバースと関わることは、私の専門である音響学という枠から大きくはみだして、学問とは何か、大学とは何か、国家とは何か、西欧とは何か、文化とは何か、人間とは何かなど、際限の無い哲学的問いを追求する良い理由付けとなり、その集大成として上梓した書籍「快感進化論―ヒトは音場で進化する―」は一つの思想を極めたという自信を私に与えた。社会の基本構造が分かったのだ。そのおかげで東京電機大学に異動してすぐに大学改編に直面したときに、何をなすべきかという答えは頭の中に出来上がっており、理系分野にもものつくりに関する文系的な視点が必要であるという主張が受け入れられ、認知科学や社会科学の習得をポリシーに盛り込んだデザイン工学科を創設することができた。現在、学科長としてその完成度を高めるために奮闘しているところである。認知科学や社会科学の習得といっても、範囲は限られる。ものつくりや人間社会の原理に焦点をあてることにより、短期間で本質的な部分を習得できることを目標とした。例えば「デザインのための社会科学」(2年次必修)の講義では暗黙知理論(技能)・中心―周縁理論(社会の構造)・過剰―蕩尽理論(祭りの原理)・神話学(トリックスター、ブリコルール)・贈与論(神の原理)・貨幣論・宗教論・ミーム論・科学論・記号論・構造主義・リベラルアーツ・進化論・ミーム論というテーマをそれぞれ1時限(100分)で説明する。特に人間および社会の理解の中核となる最初の4つ(暗黙知理論・中心-周縁理論・過剰-蕩尽理論・神話学)とミラーニューロン(認知科学)は重要であるため、「デザイン工学基礎実習」(1年次必修)の中でダンス(ZUMBA)を行うことにより実践的(身体的)に学ぶ方針とした。
― 十字型教育
デザイン工学科の創設にあたり京都大学のデザイン学ユニットの思想は大変参考になった[1]。その中で示されている十字型人材の教育方針はそのまま採用させていただいた。十字型人材とは旧来のI型人材とT型人材に対比させた教育方針である。I型人材とは直線的に専門的な知識を習得させることにより専門家の育成を目的とする。専門知識以外は習得しないため、専門バカ・タコつぼ化・サイロエフェクトが生じ、社会一般から批判の対象とされてきた。T型人材の教育とは専門知識を十分に高めた後で一般的な知識を広げ、統合的な知見を育む教育方針である。私自身は音響分野で専門を極めた後で、社会科学や認知科学などを学びながら人間や社会に関する原理を統合的に捉えてきたため、結果としては自発的にT型教育により知識を得た。十字型人材の教育とはデザイン学を横棒として、多様な専門知識を統合化することができる人材を育成する教育方針である[1]。京都大学デザイン学ユニットの場合は専門知識の枠を超えて他の人々と協力できる優れた専門家という意味を込めて十字型人材と表現しているが、東京電機大学デザイン工学科では横棒はデザイン学という曖昧な体系ではなく、ヒトや社会を統合する仕組みに関する認知科学・社会科学の知識を習得することを目標とした十字型人材の教育方針を取り入れた。さらに学部教育の初期からそれを取り入れるという意味では、従来の教養教育(リベラルアーツ)に近いが、モノ・空間・サービスの価値を社会の中で自ら評価できる能力をもつための具体性をもつため、従来の教養教育とももちろん異なる。
ところで工学教育に統合的な視点が必要という論点はもちろん私自身の主張によってはじめられたわけではなく、私が着任した当時の学長古田勝久氏が新学科創設の構想として提案したものが発端となる。また古田元学長の提案も、それまでの日本学術会議の提言[2]に影響を受けているであろう。しかしながら、知を統合するための方法論は複数の専門分野の横断的な協力体制が必要であることを述べるばかりであり、そこには知が自発的に創造される仕組みは意識されていない。京都大学デザイン学ユニットにしても複数の専門家が協力して社会的な課題に取り組むという実践的なアプローチが主な教育内容であり、やはり同様の問題を抱えている。
― 知の統合:暗黙知理論
日本学術会議の提言「知の統合‐社会のための科学に向けて‐」[2]では次のように述べられている。
”知の体系は細分化されやすいものであり、この逆らい難い流れは人文社会系、理工系に共通して及び、「社会のための科学」に対する障壁となっている。人文社会系では、複雑な社会現象の解明や対処に対して、個別化した科学相互の協力が円滑に行えていない。理工系の知は、人工環境の形成に深く関わり、社会の諸々の活動に多大な影響を与えているが、現状の細分化された知では、多岐に渡る影響の理解や洞察に限界が見られる。
こうした現状の背景には、「社会のための科学」の担い手である科学者コミュニティが知の細分化問題を十分に自覚していないということがあり、この事態は大いに憂慮される。“[2]
私はこの問題は「知」そのものが認知モデルとして理解されていないことに起因すると考える。つまり、人間の認知メカニズムがどのように働いて知が生成されるのかを理解出来なければ、細分化問題はいつまでたっても自覚出来ないであろう。私自身も複数の研究者が含まれる研究グループに参加することがあり、また京都大学にいた時もタコつぼから出ようとしない、あるいは出られない人がほとんどであることを身にしみて感じている。
そこで私はデザイン工学科の創設において「知の統合」を認知モデルとして理解するためのカリキュラムを取り入れるべきと考えた。すなわち「知」がどのように統合されていくのかという理論をカリキュラムの骨格として位置づけた。古典的な知のモデルとしてはソシュールの「記号論」およびその様々な発展形が候補に挙がるが、「統合化」という視点を考えれば暗黙知(Tacit knowing)が理論モデルとして最適である。暗黙知理論はマイケル・ポランニーが提案し、栗本慎一郎が紹介した「知」を行為として捉えたものであり、またタイトルに含まれる「周縁制御の原理」とは暗黙知を生成する境界条件の存在をポランニーが指摘したものである[3-4]。一般に「知」は知識(knowledge)という静的な状態を示しており、行為ではない。例えばI know you.と言うが、I’m knowing youとはあまり言わない。動詞+ingで表される動詞は一般にread, write, walk, runなど能動的な意思が必要であり、身体動作を伴うものである。例えば、今、あなたがこの文章を読むとき、You’re reading this sentence.と表されるが、このページを手でめくって視線を文章に合わせて進めるという身体動作を行っている。さらに目を閉じてこの文章の意味を深く考えたとする。そのときあなたはknow-ingを行っている。身体動作を伴わない(すなわち暗黙的である)が、知ることが行為であるというのがポランニー・栗本が暗黙知として見出した知のモデルの核心である。さらに、それが人間の地球上の全ての文化創造の原動力となったヒトの認知モデルと言っても良い。ひとらしさ、人間性とは何かと聞かれたときに最初に答えるべき特徴がヒトが暗黙知を有することと言って良い。
ところで暗黙知に関してインターネットなどで調べると「言葉にできない知識」と勘違いしているケースがほとんどである。これは経営学で暗黙知を用いた野中郁次郎氏の著作による影響である。言語化できる知識が「形式知」であり、言語化できない知識が「暗黙知」という位置づけであるが、これは完全な間違いである。まず、暗黙知理論に基づけば知識は言語化できないので、形式知/暗黙知というモデル自体が意味をもたない。暗黙知理論に基づけば状態としての知識は道具と同じであり、潜入(Indwelling)することにより自分の意味空間(言語的な空間)の中に統合化する対象となる。その統合化自体が技能であり、高い技能をもっていれば意味空間や実空間(身体的な空間)の中で自分の世界観を広げることが可能となる。
暗黙知は技能を用いる場面であらわれる。この文章を読んでいる読者は言語の技能を用いてこの文章を理解する能動性が無意識的に働いている。ところでどのような文章でも能動性があらわれるわけではない、自分の技能にちょうどよいレベルの文章において高い能動性が働く。文章が簡単すぎたり、難しすぎれば、理解しようとする能動性は低くなる。一般に暗黙知(技能)をより働かせるモノ・空間・道具が必要となる。
― 知の活性化:中心周縁理論
空間において境界を定めることにより、境界の内と外あるいは左と右あるいは上と下などの対立項が生じる。対立項から生じる意味は人間社会の中でコミュニケーションを生じさせ、人々の脳は活性化する。人間社会では身体の安全や維持とは別の次元で脳細胞の活性化が求められており、むしろ身体の安全や維持よりも経済効果は大きい。現代において最も強力な境界は一神教的な善悪を分ける境界であるが、実際には善悪を明確に分ける境界はできないため、瞬時的に経済効果の高い方向に善悪を分ける境界は定められる。別の見方では経済効果が高い方向に境界線を引くために一神教は利用される。我々はそのような誤った境界に翻弄され、右往左往する。日本をはじめとする多神教的な世界観では悪はそれほど否定的な意味ではない。すなわち、悪もまた良しという考え方である。例えば京都の八坂神社はスサノオがご祭神だが、その近くにやはりスサノオをご祭神とする悪王子社がある。現代的な観点では神社に悪という名称がついていることに疑問を抱くであろう。しかし、古くは悪はせいぜいいたずらものという意味であり、誰も疑問に思わなかったはずである。日本だけではなく世界中の神話において人々を困らせるが良いこともする、いたずらものの神がおりトリックスターと呼ばれている。山口昌男は著書「文化の両義性」の中で境界が定まらない両義的な存在が神話や詩をはじめとする様々な文化装置として機能していることを示した。「活性化」という言葉自体、山口昌男が社会科学の中で使い始めたのだ。さらに社会を活性化する境界が周縁である[5]。
一般にモノやヒト、イミにおいてよく知らない状態と、よく知っている状態の間になんとなく知っている状態がある。なんとなく知っている状態のモノ・ヒト・イミはよく知っている状態に遷移する可能性をもっており、暗黙知理論でいえば諸細目として認知している状態が包括的全体へ遷移することにより、その対象物のことを「分かった」ということになる。トリックスターという両義的な存在は対立項の間をいったりきたりするため、分かったようで分からない存在である。それが分かってしまえば、対象物は中心へ引き寄せられて周縁には存在しなくなる。例えば最初に自転車に乗れるようになったことを覚えているだろうか。自転車の技能の獲得過程は暗黙知理論の説明などでよく用いられるが、例えばハンドルの操作、ペダルの踏み方、サドルでの重心のかけ方、視聴覚や体性感覚から得られる情報などが諸細目となり、それが包括的全体へ遷移して統合化されることにより、自転車の乗り方という技能が身につく。自転車に乗る技能を獲得し、自転車に潜入することにより、身体化される。自転車に乗る技能が完全に身につけば、次は路面の状態がよく分かるようになり、路面の状態によって運転の仕方も変わってくる。さらに自転車で近所を回れるようになれば、次第に行動範囲は広がり、自分の家の区画からまち全体の空間へと潜入の空間範囲は広がる。
ところで最初に自転車の技能を獲得しようという能動性はどのように生じたのだろうか。自転車に乗れる動物としては熊があげられる。サーカスなどで熊が自転車を漕いでいるのを見たことがあるかもしれない。ただし、熊は調教されて自転車に乗れるようになったのであり、自発的に自転車の練習をしたのではない。一方でヒトは自発的、能動的に自転車に乗るための技能を獲得する。自転車の乗り方が「分かった」という状態になりたいからである。つまり、それまでは自転車の乗り方はなんとなく知っている状態だったといえる。周辺の大人やお姉さん、お兄さんが自転車に乗っているのを見て、自分も乗れるかもしれないと感じたはずである。そのときに自転車は周縁的な存在だったのである。自転車に乗れるようになった瞬間に、自転車の乗り方への興味はなくなったであろう。すなわち自転車は周縁から中心的な存在になり、自転車の技能獲得によって得られた近所の空間、さらにはまち全体の空間へと周縁は変化していく。
一般に技能獲得のための暗黙知を発動させる対象は周縁的な位置に存在するといえる。したがって、社会において我々が創造するモノ・空間・イミは、できるだけ多くの人ができるだけ長い間、周縁的存在として位置づけられるようなものが高い価値をもつ。多神教的な価値観に両義的な側面があるのは、永続的な周縁性を生成するための知恵であることが分かる。
― 祭り:過剰蕩尽理論
マルセル・モースの贈与論によれば「贈り物には霊的な力が宿っており、贈り物はもとの所有者や聖所に戻りたがるという性質ももつ」。誰かから贈り物を受け取ったときに、返礼をしないと祟りがあるということである[6]。誕生日や記念日などで贈り物をもらった場合には返礼の義務を感じることから、これは心理的には極めて自然である。経済活動の心理的な原点は贈与により互酬が生じることにあると考えられる。これは経済の原点が市場にあるとされる近代的な経済学の視点とは対立する。市場や貨幣が成立するはるか以前から、地球上のヒトは互酬により経済活動を行っていた。
ところで我々は自然界から食料や道具の材料を与えられてきた。自然界から一方的に与えられるそのような贈与を中沢真一は純粋贈与と呼ぶ[7]。返礼の義務をこなさなければ、災厄がもたらされるという自然の心理が、お祭りを行う動機となる。すなわち、お祭りで行われている行為は全て返礼を意味しており、その相手が神である。神に対する定期的な返礼としてお祭りを行うことが、ヒトの集団において義務付けられており、通常よりも大きな災厄があれば、神への返礼が足りないのではないかという疑問がもたらされる。
ヒトの集団が日常生活の中でお祭りという非日常を催すことにより、過剰を蕩尽する。日常生活でたまっていたヒトの集団の不満をお祭りにおいて一気に解消することが、神への返礼にもなる。すなわち非日常では日常に守られてきたルールが破られる。ポトラッチではヒトの集団が隣の集団と競い合ってモノを消費(蕩尽)し、より多く消費した方が優位となる。古くは戦争で捕らえた奴隷を犠牲にする人身供犠、人身御供が行われていたこともある。すなわち戦争の目的は現代のように利権争いではなく、人身御供が目的だったというのが、ジョルジュ・バタイユの過剰-蕩尽理論から得られる結論である[8]。したがって、日常は非日常のためにあるか、非日常は日常のためにあるかという質問に対して、お祭りをよく理解しているヒトは前者と答える。日常生活はお祭りという非日常が起点となって、あるいは次のお祭りという非日常を目的として、執り行われる。日常生活を平穏にすることを目的として非日常的なイベントを企画するのではない。これは現代にも当てはまる。我々が日常生活を行うのは、非日常的なイベントを行うことが大きな目的なのだ。それがひとらしさを保つための秘訣となる。
京都大学にいたころに修士課程の学生(吉田君)でハーレーダビッドソンを購入した者がいた。男の子の誰もが憧れるアメリカンバイクである。150万円したという。大学での教育・研究をこなしながら、アルバイトをして、食うものも食わず貯めたお金で購入したのだ。地方での学会で発表した時にも彼はハーレーに乗ってやってきた。彼にとってハーレーは非日常であり、周縁であり、蕩尽の対象である。ハーレーという非日常を得るために、日常生活をこなしてきたのだ。彼はひとらしさを保つための現代的な方法を理解していたといえる。
― むすび
トラバースという場は私にとっては暗黙知が発動される場であり、周縁であり、過剰が蕩尽される場である。トラバースに参加した先生方と語り合うことが「知の統合」に向かっていった場であった。これまで私は多くの研究グループに所属してきたが、なかなかこのような「知の統合」は生じない。専門家が集まって協力するだけでは、「知の統合」は生じない。トラバースに参加していた先生方は本能的に高い暗黙知を実践しており、周縁の世界に生きていたため、それが化学作用を起こして「知の統合」が生じたのだ。はじめにでも述べたがこれは私にとっては本当に幸運なことだった。
【参考文献】
1. 十河卓司、京都大学デザインスクールでの博士人材の育成、計測と制御、 Vol. 54、7、2015.
2. 中島尚正、提言:知の統合-社会のための科学に向けて、日本学術会議対外報告、2007.
3. マイケル・ポランニー、 暗黙知の次元 言語から非言語へ、 紀伊國屋書店、 東京、 1980.
4. 栗本慎一郎、 意味と生命、 青土社、 東京、 1988.
5. 山口昌男、 文化と両義性、 岩波書店、 東京、 2000.
6. マルセル・モース、贈与論、筑摩書房、2009.
7. 中沢新一、 神の発明 カイエ・ソバージュ、 講談社、 東京、 2003.
8. ジョルジュ・バタイユ、 呪われた部分、 二見書房、 東京、 1973.
伊勢史郎 Shiro ISE
Born in Tokyo, Japan in 1961, Shiro ISE is an acoustician and professor of the faculty of information environment in Tokyo Denki University. He studied acoustics and received M.S. in 1988 at Waseda University, and Ph.D. in 1991 at University of Tokyo. While he worked for Nara institute of science and technology from 1994 to 1998 as a research associate, he stayed at Cambridge University in U.K. as a visiting scholar to study fluid acoustics from 1996 to 1997. Then he stayed at Kyoto University as an associate professor of architectural acoustics from 2003 to 2013. He mainly studies active noise control and sound field reproduction experimentally, theoretically, and numerically. Recently, he is interested in the psychological research on the mental action of the sound in “the sense of unity”.