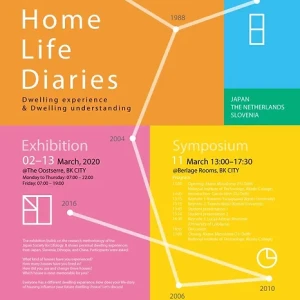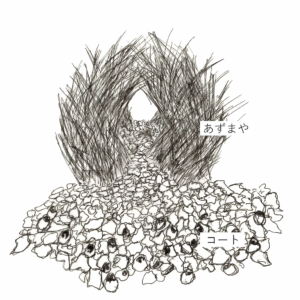ガパオライス|山井駿
午前7時。目覚まし時計が鳴るより早く、バイクの喧しいエンジン音で目を覚ます。カーテンを開けると、摂氏30度の光が飛び込んでくる。最高気温は40度。その表示に目が慣れてきたのだから恐ろしい。今日もまた下階のガパオ屋のおばちゃんの大声を聞きながら、ゆっくりと歯を磨く。

M1の冬。組織設計事務所の就活に落ちた僕は、アトリエのインターンで東京にいた。優秀な先輩が薄給激務に苦しむ姿を目の当たりにして少し疲れた僕は、夜の渋谷をうろついていた。キラキラと光る公園。パブリックスペース。その程近くに、泥酔したおっさんが地を這う、人間の欲や弱さや醜さ、それ故の愛おしさすら感じる雑踏。どちらが人間的か、どちらが「パブリック」か、考える。そしてデザインがそこに及ぼす功罪の不可避に、戦慄する。同時に、つい夕刻までのアトリエの苦境がフラッシュバックし、僕の中で一つの問いに収束する。「誰のためにデザインは在るのか」。そこからタイへの留学を決めるまでに、そう時間はかからなかった。
保存と宗教

セメスター前の年末年始、アユタヤに一人旅に出た。中心部を一通り巡った後、世界遺産区域の外側に位置する遺跡を目指すことにする。炎天下、ローコストに釣られてレンタサイクルを選んだ自分を呪いながら、野犬とカーチェイスをし、なんとか目的地に至る。そこは寺院学校の併設された、閑静な場所だった。約250年前にビルマによって破壊されたアユタヤ。その遺跡の多くは、天井がなく、壁も崩れた状態で今も時間が止められている。この遺跡も例に漏れず、本堂の基壇すら大きく歪んでいた。しかし、崩れかけた門を潜り、日が射した内部に入った瞬間、それを一生忘れることはないだろうと思った。崩れ落ちた空間の中、焼け焦げた仏像に鮮やかなオレンジ色の袈裟が掛けられ、地元の人びとが跪いて手を合わせる。純白の着物を纏った寺院学校の少女たちが、凜とした足取りで仏に花を運ぶ。建築がその形を失いかけてもなお、そこで行われてきた祈り、人びとの行動は、何百年の時を超えて継承されている。建築はもはや場所以上の何物でもない。そう実感して、何故か無性に嬉しくなった。

バンコクで訪れたいくつかの場所では、宗教に留まらない寺院の役割をいくつも目の当たりにした。寺に遊びに来る女の子に毎日20バーツの小遣いをやる住職。日曜日になると伽藍内の空地いっぱいにマーケットが展開され、僧侶が読経する壁一枚隔ててiPhoneのパチモンが800円で売られる寺院。野犬から逃げて道に迷った僕を駅まで送ってくれた同い年のお坊さん。宗教と日々の生活は不可分で、寺院はときに単なる空地として、ときにコミュニティの拠り所として機能する。そんな柔軟さに驚かせられた。

タイ北部・スコータイでは、市街地であるニュータウンと、遺跡と農村が混在するオールドタウンが12kmの距離で隔てられる。保存を越えて完全に保護された遺跡群は、不気味なほどに静まりかえり、農村との関係すら絶たれて見える。
カンボジア出身の親友の祖母の家系は、長くアンコールワットの境内に住んでいたそうだ。世界遺産登録が決まると一転、ろくな補助なしで追い出された。「観光そのものが暮らしを変えるのではない。観光に対する政策が変えてしまうんだ。」彼はこんなことを言っていた、ような気がする。
4月に周遊したマレーシアは、中国/マレー/ムスリム/ヒンドゥーなど多文化の併存する世界だった。何でも収斂してしまうようなタイとは違い、各々が独立しながら隣り合っている感触。北部ピナンと南部マラッカでは文化圏の構成もまるで違う。マレー人でムスリムのタクシーの運ちゃんが、俺はアラビア語が分からない、そう言うので驚いた。どうクルアーンを詠むのか、どう他のムスリムとコミュニケーションを取るのか。「心で通じ合えるのさ」そう答えられて、不可解な顔のまま相槌を打った。
あるモスクでは、建築や宗教について丁寧に解説してもらえた。モスクの色にもトレンドがあること。結婚式場と葬儀場が隣接していること。教育から冠婚葬祭まで、人生の殆どの行事がモスクで完結されること。気さくなおっちゃんのガイドで印象に残っているのは、一日5回の祈りを「歯を磨くのと同じ」生活習慣だという台詞、そして異邦人である僕らを垣根なく無償でもてなしてくれた、意外なほどの寛容さ。イスラム教に対する理由のない恐れを初めて自覚し、同時にそれが取り払われた瞬間だった。
保存とは何か。宗教とは何か。生活という観点から、その偏見や固定観念を悉く破壊された旅路だった。

観光
バンコクから車で7時間。スリンという田舎町がある。タイの中でも特に貧しい地域、そのさらに外縁に位置する場所へと向かった。目的地はエレファントワールド。象のショーや体験といった観光アクティビティで、地域の再生を目指す施設だ。

ArchDailyにも掲載されるその建築。露出するパイプ、非合理な雨仕舞、そんなディテールの不備は大した問題ではない。使われていないのである。象の行動や住環境が考えられていないからか、全てのアクティビティが旧来の施設で行われていた。 “The Cultural Courtyard”と名付けられた空間の屋根は、メンテナンス不足で朽ち果て、鳥の楽園と化していた。周囲にはホームステイも商業活動も根付いていない。象の生態や周辺のコミュニティに対するリサーチの不十分は、現況を見れば明らかだった。観光を統括する政府と施主、建築家の間でコミュニケーションが上手く為されていれば、状況は違ったのかもしれない。ただ、「誰(象を含む)のための建築か」、その問いがあまりに議論されていなかった。建築家が、あるいは建築が、ここでは必要ないように思えた。一つの名建築が地域を変える、日本でもしばしば語られるそのストーリーが完膚なきまでに否定される状況を見て、愕然とした。
観光業に力を注ぐタイ政府。バンコクやプーケットといった主要都市は、旅行者数の世界ランキングでも上位に入る。高価な座席と、タイ人専用の安価なフェンス裏立ち見席に二分されるムエタイ競技場。外国人で溢れ、住人らしきタイ人を見なかったプーケットのPatong。急激に成長する観光産業の歪みも、確かに感じられた。

僕が修士研究で扱う運河沿いのマーケットも、新たにテーマパーク的につくられたり、生活や産業の構造が観光地化で完全に変わったりしている。それをジェントリフィケーションの一言で片付けるのは簡単。しかし、それの何が問題だろうか。たとえテーマパークでもそこに商業は確かに生まれ、そうして今日を生きられる人がいる。一度はゴーストタウン化した集落に、観光によって再び人が帰ってくる。その地域の経済が豊かになる。運河という資源で今日を生きる営みが続くというのは、案外その構造は以前とそう大差ないかもしれない、とすら思えてくる。ギリギリに、それでも笑顔で生きる人びとの前で、歴史的に何が正しいか、その議論自体正しくないように思えてしまう。

ニューハーフショー
学生にとっては大きな1000バーツ(4000円)を払って入った会場は、やはり学生向けのものではなかった。派手な赤色証明に照らされたシアターに円卓が並べられ、いかにも金持ちそうな外国人が周囲で談笑する。酒を飲んで開幕を待つ間、どうそれを観るべきか思案していた。マイノリティと呼ばれる人びと。そのことを売り物にしたショーを好奇の目で観るのは果たして倫理的なのか。そんな葛藤は、開演するやいなや粉砕された。彼らは自分を見せることで、生きていた。自分を演じる誇りを感じた。その強烈な自我を前に、ジェンダーの領域はもはや問題ではなかった。それに素直に魅せられ、笑い、驚く。それが彼らへの、彼らの生き方への何よりの賛辞だと思った。

スラムと言語
バンコクからロットゥー(交通マナーの概念がない爆速の乗合バン)で1時間ほどにあるタマサート大学、UDDIという都市デザインコースに留学していた。香港出身のAdrianという少しデリカシーの欠けた、しかし気のいい教授から課されたスタジオのお題は、スラム移住地の計画だった。タイではCODIという公共機関の行うBaan Mankong Programというスラム改善事業が行われている。その実際のプロジェクトに取り組み、デザインをCODIとコミュニティに対して提案するという実践的なものだった。
それは想像を絶するほど過酷なプロジェクトだった。線路沿いに黙認されながら住んでいた169家族が、SRT(タイ国鉄)によって突如強制移住を命じられる。十分な補助がない上に、移住先は高速道路と汚染された運河に挟まれた狭小地。しかも、30年後には再開発のあおりで、再びその土地をSRTに譲渡しなければならない。僕らはその条件下、オープンスペースや換気通風(もちろんエアコンをつける予算はない)を軸として計画を考えた。30年後の交渉材料にもなるようにプランを練った。

そしてCODIへの中間発表の前週、プロジェクトの中止が言い渡される。コミュニティは土地を一刻も早く安価で得ることを優先し、SRT側の提示した箱を並べただけの提案を選んだ。もう僕らの提案が役立つことはない。そんな事情だった。
建築の無力を知った。コミュニティ側の思いは間違いなく切実なもので、そうならざるを得ない状況に問題がある。十分な補助や配慮を与えないSRTが悪い。けれども、その根本には、人びとが都市に集中し違法に住まざるを得ない、都市と農村の格差がある。問題は、建築家が、いや誰もタッチできないような領域まで膨れあがっていく。建築家はスーパースターではなく、それに場当たり的に対処する小さな存在でしかない。
その時、直接に「建物」に触れる立場として建築家は、何ができるか。

最後に、まとまらないこの文章を、この問いを投げかけて終わりにしようと思う。
「誰のためにデザインは在るのか」と。