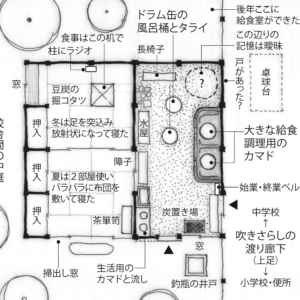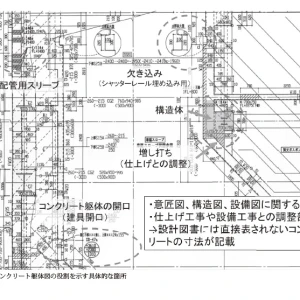日記|辻 京佑
九月十三日 水曜日 三徳山三佛寺 投入堂
数々の寺院を撮影してきた写真家・土門拳をして「日本第一 の建築は?と問われたら、三仏寺投入堂をあげるに躊躇しないであろう」と評される、鳥取県東伯郡三朝町に位置する三徳山・ 山仏寺へ参拝に行った。奥宮である投入堂は「日本一危険な国宝」という別名でも知られ、その道は余りにも過酷だ。木の根が絡み合ったかずら坂に始まり、急峻な山路を超え、一瞬ためらってしまうような大岩の凹みに足を掛け、登っていく。極め つけは体感でほぼ直角なのではないかという鎖場である。崖にぶら下がった鎖を支えに、天を見上げて一歩一歩、ゆっくりと進んでいく。鎖を掴んでさえいればどうということはないが、 万が一手を離せば、すぐさまあの世行きである。道中に構える文殊堂と地蔵堂も同じく懸造で、柵の無い欄干を一周することができる。もちろん、こちらも滑落墜落すれば命の保証はない。
終盤の納経堂の裏側を「胎内くぐり」によって通り抜け、数分歩くと、突然視界が開ける。ついに投入堂と対面することに なる。

土門は後年、脳出血によって右半身不随となるのにも関わら ず、この険しい参詣道を何十回も通った。常人で1時間半ほど かかるところを、土門は3時間以上かけて登ったそうだ。それもそのはずだ。全く見飽きることがない。何時間でも見ていられるような建築であった。
投入堂がその存在感を強く放つ原因はいくつかあるだろうが、一番大きいのは「軽やかさ」ではなかろうか。人を拒むような崖に建っているわけだが、しがみついているという印象は 全くない。むしろ、まるで天人がふわりと崖に降り立ち、堂に姿を変えたのではないか、とすら思う。役行者が山の麓で建て た堂を法力で小さくし、崖に投げ入れたことが名の由来とされ ているが、言い得て妙である。
もちろんこれは、斜めの筋違を入れることで材を最小限に保っていることや、身舎柱に比べて庇柱が細くなっていることなど、構造から起因するものである。特に、現在は投入堂の前 に柵があるため、右斜め下からしか眺めることが出来ない。したがって、細い庇柱が手前にくることになり、「軽やかさ」を増す一因となっている。
投入堂のすらりとした佇まいは、どっしりと構えている多くの寺院建築(清水の舞台ですら例外ではない)に見慣れた我々の感覚を洗練させる。
麓の宝物館では、大正時代の改修で取り外された投入堂の古材が保存されており、「附」として国宝に指定されている。投入堂の前を落ちる水しぶきで著しく腐食した古材であるが、その姿は今もなお迫力を保っている。正直に言って、全ての現代建築は洗練具合で投入堂に勝てていないと感じた。それくらい魅力的な建築なのである。ただしそこまでの道のりを考えると、私はしばらく行きたくない。
十月十四日 土曜日 ケベス祭
皆さんは大分県が誇る奇祭「ケベス祭」をご存じだろうか。 ケベス祭とは、交通の便の悪さから「陸の孤島」とも揶揄される国東半島の先端、国見町櫛来にある岩倉八幡にて、毎年10 月14 日に行われる火祭である。
ケベス祭の前半は、火を狙って突入する「ケベス」と、それを防衛する「トウバ」の攻防から成る。トウバは複数人おり、岩倉八幡の氏子である10の集落が持ち回りで務める。祭当日、その年のトウバに所属する成人男性の中から、ケベス役が選出される。ケベス役は、「ケベス面」をつけられ、神官から背中に「勝」という文字を指で書かれる。神官が背中を叩くと、「ケベス」が憑依し、祭が始まるのである。その後、境内の端に山積みされた柴に火がつけられ、瞬く間に空に届くほどの大火となる。そして、神官たちが太鼓・笛・鉦から成る音楽を奏でながら、境内を回り始める。ケベスは神官たちの後ろについて境内を回っているのだが、あるところから隙を伺い始め、突然、火に向かって突進する。火前にいるトウバはそれを阻止するためにケベスともみ合いになる。阻止されたケベスは神官たちの列に戻る。その繰り返しである。ケベスは列に戻るふりをして不意打ちを仕掛けることもあり、迫力満点である。
ケベスとトウバの攻防が9回目に達すると、祭は後半へ転ずる。それまで火を守っていたトウバは突如として手に持っていた棒を焚木の中に突き刺し、われわれ観客に向かって火の粉をばら撒き始めるのである。この火の粉を被れば無病息災になれるというが、その勢いが尋常ではない。地面に置いていた荷物の上にバスケットボール大の火の玉が落下し、鞄は丸焦げになってしまった。ご利益のある鞄になったのだろうが、鞄として使えなければ意味が無い。髪の毛の先端に引火してチリチリになることもあるし、化学繊維の服に火の粉が落ちて穴が空くことも多い。祭の前に、我々の都合など通用しない。

興味深いのは、ケベス祭の由来、そして「ケベス」が何者なのか、その一切が分からない点である。人々は伝統に則り、祭りを遂行するのみだ。そうして数百年が経過した。
ケベスの由来には、鍛冶神たる宇佐八幡に関連する、神功天皇の朝鮮出兵に関連するなど、様々な説がある。「ケベス」がヘブライ語で「羊」を表すことから、ユダヤ文化との関連も疑われているが、詳細は一切不明である。しかし、彼らの振る舞いを見るに、由来は既に重要ではないことは容易に推察できる。既にある規則に基づき祭を遂行する。その中で小さな変更があり、時間の経過で集積していく。おそらく、現在のケベス祭は「本来のケベス祭」とは全く異なった形式なのであろう。数百年先のケベス祭も全く異なったものかもしれない。しかし、ケベス祭は人々の手で執り行われていると同時に、既に人々の手を離れている。そして、人々の生活そのものなのである。ケベス面は、異なる高さに目が彫られている。従って、「ケベス」は、片目しか見えていない。石川直樹氏の著書『地上に星座をつくる』のなかで、神は身体が不自由である場合が多く、ケベスもその一例、つまり越境者なのではないか、という仮説が述べられているが、その真偽はもはや知る由もない。片目のケベスが見る炎は、果たして我々が見る炎と同じなのだろうか。
十月十五日 日曜日 シシ権現
シシ権現は大分県臼杵市の山奥に存在する神社である。大分県というのは実に興味深い地であると常々思う。シシ権現への道の途中には、土門拳が『古寺巡礼』のなかで「石仏の中でも特に好きである」と語る、国宝・臼杵石仏が鎮座している。現在は修復が行われているが、土門が撮影した時点は野晒しになっており、多くの仏像が風化、頭部の剥落があった。それを好みと断言する土門の並々ならぬ美的感覚がよく表れた逸話である。
話を元に戻そう。シシ権現とは、ひとことで言えば「猟師が獲物を奉納する神社」である。シシ権現は熊野神社の奥の崖を登った先の洞窟に存在し、その中には数千におよぶ鹿と猪の頭骨が奉納されている。頭骨のなかには、猟師が獲物を狩った日付を書いているものがあり、その中には令和のものも含まれる。堆く積まれた頭骨の重さや、偶に訪れる参拝者によって、下部の骨は砕け散り、砂利と化している。一度見たら忘れられない光景である。ちなみに、投入堂ほどではないが、高さ50mほどの鎖場があり、落ちれば死ぬ。

シシ権現は正式名称を「白鹿権現」といい、毛越寺縁起としても伝えられる白鹿伝説に狩りの要素を足した由来が伝わっている。シシ権現の頭骨はかなり丁寧に積まれており、猟師の信心深さが伺える。しかし、入口の鳥居の注連縄は千切れて落ちていたり、神社に向かう途中に定期的に猟銃の発砲音が聞こえたり、不安に満ちた参道であることは間違いない。

シシ権現に来ると、聖地とは何か考えさせられる。古来より我々は、人の手が及ばないものを神として崇めてきた。沖縄の糸満にある斎場御嶽では、巨石から下がる二本の鍾乳石から滴る水滴を壺に溜め、「聖なる水」として儀式に用いた。ケベス祭は詳細不明ながら、火を祀っていることは明らかである。シシ権現は、獣の命を人間の死生観に基づいて祀る。アイヌのイオマンテも同様の性質が認められるだろう。
我々は普段、文明の中に生き、様々な職業に就き、他者から金を貰って生きている。建築というのは、設計によって他者の挙動を制御する職業であるから、文明の概念を代弁しているようにすら思える。しかし、我々はいま一度、自分たちがどこに立っていて、どこに向かおうとしているのかを考えなおす必要がある。「聖なるもの」は、その出発点に過ぎない。
参考文献
土門拳, 1989『, 続 死ぬことと生きること』, 築地書館
石川直樹, 2020『, 地上に星座をつくる』, 新潮社