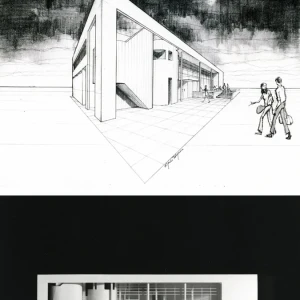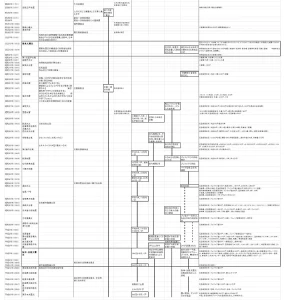ヒューマン・ウェブの未来:COVID-19とステイ・ホーム|布野 修司
<巣>といえば、鳥・獣・虫の棲家である。一般に、動物が自らつくって産卵、抱卵、育児または休息、就眠に使用する構造物や穴をいう。人の住まいも<巣>であるが、二人の「愛の巣」とか、盗賊の「巣窟」のように、ある特定の集団の秘密めいた場所というニュアンスを伴う。日本語の<住む>は、<栖む><棲む><澄む><清む><済む>と同根とされるが、<巣む>とはいわない。英語の<巣 nest >は、類義語として den, beehive, aerie, cobweb, rookery などが挙げられるから、やはり鳥・獣・虫の棲家のイメージである。一般的な住居は house,home, dwelling である。
<巣>といっても、その形態はさまざまである。哺乳類 ( カヤネズミ、ビーバーなど )、鳥類 ( ハタオリドリが有名 )、魚類 ( トゲウオなど )、昆虫類 ( 白蟻、蜜蜂など )などがつくる<巣>は見事である(図 1abcd)。ゴリラやチンパンジーでも、毎日夕方に樹枝で就眠用の巣をつくる。チンパンジーは、二度と同じベッドに寝ないというから、日々簡易な巣をつくるということである。マダガスカル島のリスザルは、自分の糞で球形の巣をつくり、樹上に運び上げる。鳥類の中にも、天然の穴や樹洞や動物が掘った穴をそのまま利用し、何も持ち込まないで産卵するものがある。
『東南アジアの住居 その起源・伝播・類型・変容』(布野修司+田中麻里+ナウィット・オンサワンチャイ+チャンタニー・チランタナット,2017 年)で触れたけれど、これらの動物が示す精巧な造巣行動 ( 造巣技術 nest-building) のほとんど全ては遺伝的にプログラムされたものである(序章 ヴァナキュラー建築の世界 2住居の原型)。ただ、興味深いことは、E. ギドーニの『プリミティブ・アーキテクチャー』(Guidoni, E.(1975))を見ると、見事な動物の巣のような、しかしヒトがつくった住居が並んでいる。中央アフリカやマリ、エチオピアなどの、小枝と藁と土でつくられた穀物倉など、実際、鳥の巣箱に見えるようなものがある(図 2 ab)。建築におけるバイオミミクリーへの関心は、専ら形態の可能性に向けられているようにも思えるけれど、場所の生態学的基盤に基づく設計方法の展開にとって、生き物たちの<巣>に学ぶことは少なくない。
<クモの巣>=ウェブ Web は、捕獲装置であって<巣>ではない。本稿のキーワードは、ヒューマン・ウェブ(人と人を繋ぐ種々の結びつき)である。




図1 abcd アフロ 布野修司他( 2017 )
― 平成という時代-グローバリゼーションとCOVID-19
住居は建築の原点である。ヒトの場合、住居をつくる技術は、遺伝的にプログラムされてはいない。98.8%遺伝子が同じだというチンパンジーは住居をつくらないが、1.2%の DNA の違いに住居建設の能力が関わるということではおそらくない。20 世紀に至っても、裸のままで 1 万年前と同じように暮らす人がいたということは、住居の建設能力は遺伝的プログラムに依存するより、経験と学習、文化に属するということである(A. ラポポート(1987))。地域の自然、社会、文化の生態によってその形態が異なるのはそのことを示している。建築(住居)とは、自然の中に人工的な空間をつくり出すことに他ならない。雨風を避け、寒暖の制御を行いうる覆い(シェルター)がその起源である。人工的空間をつくり出すために用いられるのは身近にある材料である。
「51C」(公営住宅の標準設計 1951 年 C 型)という戦後住宅のプロトタイプを設計提案した吉武(泰水)研究室を出自とする因縁もあって、これまで住居のあり方については一貫して考えてきた。


図2 ab アフロ 布野修司他( 2017 )
『スラムとウサギ小屋』(1985 年)『住宅戦争』(1989 年)『住まいの夢と夢の住まい ・・・ アジア住居論』(1997 年)などを書き、そして『日本の住居 1985,戦後 40 年の軌跡とこれからの視座』(1985 年)、『見知らぬ町の見知らぬ住まい』(1990 年)、『日本の住宅戦後 50 年』(1995 年)、『世界住居誌』(2005 年)(『世界住居』胡恵琴訳,中国建築工業出版社,2010 年 12月)などを編んできた。学位請求論文『インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究—ハウジング計画論に関する方法論的考察』( 東京大学,1987 年)を一般向けにまとめた『カンポンの世界』(1991 年)も住居論である。
これまで戦後住宅をめぐって発言してきたからであろう、「平成」時代(1989~ 2019)を総括する論文を求められた。一つは、Ebisu Ebisu. Études japonaisesという日仏会館Maison Franco-Japonaise が出している雑誌で、「平成」時代の建築家(その役割、その社会的地位、実践(作品)そして生産(成果))を振り返る企画であり 1、一つは『果てしなき現代住宅(仮)』という平成の住宅を総括する単行本の企画である 2。
「平成」時代を振り返るにあたって、まず、問題となるのは、「元号」という、一人の天皇の在位期間によって、建築や住宅の歴史を区分できるのか、ということである 3。しかし、どうやら「平成」時代は、そのまま世界史の時代区分になりそうである。第一に、ベルリンの壁の崩壊(1989 年 11 月)、ソ連邦の崩壊(1991年 12 月)すなわち冷戦構造の崩壊がある。ロシア革命(1917 年)を起点とする社会主義世界建設という人類の壮大なる実験の失敗が確認されることによって、資本主義世界の優位が明らかになり、以降、アメリカ合衆国が世界全体を主導し、本格的にグローバリゼーションの時代が到来することになった。「平成」の始まりは、世界史的大転換の年と一致する。そして、COVID-19 によるパンデミックが世界史的な区切りになることは確実である。
1 拡散する「建築家」像―アーティストか?アーキ・テクノクラ―トか?コミュニティ・アーキテクトか?Diffusing Idea of
Architect-Artist? or Archi-Technocrat?, or Community Architect?,”Ebisu ”, Maison Franco-Japonaise. 近刊予定。
2 「失われた終の棲家──君は何処に棲むのか?」フィルムアート社、近刊予定
3 日本では「明治建築」「大正建築」といった時代区分が行われてきた。長谷川堯(1937~2019)の『神殿か獄舎か』(1972年)は、そうした時代区分によって、日本の近代建築の歴史を鮮やかに描き出すものであった。すなわち、西欧の建築技術を国家的目標(文明開化、殖産興業)に導入した「明治」時代から、建築家という自己の表現としての「大正」(大正デモクラシー)時代への転換は、建築史としてもくっきりと叙述できるのである。しかし、「昭和」時代は、明らかに一括することはできない。戦前と戦中で、建築の歴史は大きく切断される。そして、戦後の「昭和」も一括りにはできない。戦後復興から高度経済成長期にかけて、戦後建築が全面開花した1960年代と、2度のオイルショックに見舞われた1970年代とでは全く様相を異にする。さらに、1980年代後半から再びバブル経済が日本を世界の主役(ジャパン・アズ・ナンバーワン)に押し上げる。そして、バブルが弾けた。
― 宙に浮くnLDK-閉じていく住居
日本が、この間一貫して、世界経済における相対的地位を低下させてきたことは覆うべくもない。日本の一人あたり名目 GDP(国内総生産)は、1990 年代前半には、アメリカ合衆国を抜いて世界一となった。しかし、バブル経済が崩壊した 1992 年以降、GDP の成長率は年平均1%前後で推移する。「平成」の 30 年間がまったく新たな時代に移行してきたことは明らかである 4。吉見俊哉(2019)は、「平成」は「失敗の時代」だったといい、「失われた 30 年」という 5。
ステイ・ホームというけれど、日本のホームは、そもそもステイする場所足りえてきたのか。平成の住宅を振り返ると、実に奇妙な流れをいくつも指摘できる。実に不思議に思えるのは、少子高齢化が急激に進行してきたのにも関わらず、nLDKモデルの住宅が建てられ続けていることである。また、空き家が増え続け、1000万戸を超えたにも関わらず、過剰に住宅が供給され続けていることである。
平均世帯人数は、3.45 人(1970 年)、3.01 人(1990 年)、2.44 人(2018 年)と一貫して減少してきた。最新の国勢調査(2015 年)によれば、総世帯数 5333万世帯のうち、夫婦のみ世帯が 1072 万世帯(20.1%)、そして、単独世帯が1842 万世帯(34.5%)、合わせれば、54.6%にもなる。夫婦と子どもという本来の核家族が 1429 万世帯(26.8%)、片親と子ども世帯が 475 万世帯(8.9%)である。さらに、拡大家族世帯が 456 万世帯(8.6%)、非親族を含む世帯が 46 万世帯(0.9%)、統計数字だけからも世帯の多様化ははっきりしている。マイホームの夢がフィクションと化して久しいのである。数字が指し示すのは一人で終末を迎え
る住居である。
1968 年に総住宅数が世帯数を超えて以来、空き家は増え続け、70 年代末には268 万戸(空き家率 7.6%、1978 年)、平成元年には 330 万戸、21 世紀初頭には846 万戸(13.5%、2013 年)、平成末には 1083 万戸(17.0%、2018 年)と推移し、世帯数の減少も加速して、2033 年には 2166 万戸が空き家となると予測されている。膨大な空間資源を有効利用するためにリノヴェーションは必須であるにも関わらず、住宅産業がターゲットとするのは、nLDK を積み重ねるタワーマンションである。
タワーマンションが林立する一方で、増加しつつある貧困者層の受け皿となってきたのは木賃アパートや「ドヤ街」である。また、ホームレスやネットカフェに寝泊まりする「ネットカフェ難民」の増加も指摘される。日本の貧困率は、15.7%(2016年)で、今や先進諸国の中でも高い。
タワーマンションを可能にした背景には、建築構造技術の発展がある。そして、超高層で住生活が可能となるためには、建築環境設備の発達が不可欠である。超高層と共に、人工環境化していく都市の象徴となるのは、季節や天候に限らず、いつでも試合や催しができる空調設備を備えたドーム建築であるが、住宅についても追及されてきたのは、冷暖房完備の高気密高断熱の住宅である。

図3
4 日本のGDPは、1955年から1973年までの高度成長期には年平均10%程度の成長を遂げた後、減速するが、それでも1975年から1991年の年平均4%の成長率であった。
5 吉見俊哉(2019年)は、世界の企業の時価総額ランキングを1989年と2018年で比較し、平成元年には、上位50社のうち33社が日本企業であったのに、30年後には35位のトヨタ自動車のみであることを指摘する。
― ヒューマン・ウェブ
COVID-19は、住まいのあり方、地域のあり方、自治体、医療体制、教育体制、学会、国家、国際機関、……世界を成り立たせているあらゆる仕組みを揺さぶり、再考させつつあるが、最大の疑問が投げかけられるのはこの間一貫して世界を主導してきたグローバリゼーションの流れである。人類とウイルスとの共生関係がその進化の起源に遡って確認され、14世紀の黒死病や20世紀初頭のスペイン風邪など感染症によるパンデミックの歴史が振り返られるが、感染拡大の速度と規模は人類史上初めての経験である。治療薬そしてワクチンの発見製造について予断は許されないが、COVID-19との共存関係が構築されたとしても、次のウイルスが出現することはごく自然に想定される。COVID-19が突きつけるのは、ワールド・ワイドのヒューマン・ウェブのあり方である。『疫病と世界史』を書いたマクニール,W.H.(1985)は、さらにヒューマン・ウェブのあり方を軸にグローバル・ヒストリー(世界史 人類の結びつきと相互作用の歴史)を書いている(マクニール,W.H.・マクニール,J.R.(2015))。
「平成」時代を特徴づける第二は、情報伝達ICT革命によるネットワーク社会の到来である。ヒューマン・ウェブの成長、変化の最も大きな要因となるのは交通手段(ウマ、船、蒸気機関車、蒸気船、自動車、飛行機)であり、情報伝達手段(言語、文字、電信、電話、インターネット)である。1989年に地球規模のインターネット(TCP/IP)ネットワークが成立し、1995年には商用利用が開始される。インターネットの利用は瞬く間に世界の津々浦々に普及することになった。そして、パソコン、携帯電話(モバイル・フォン)の進歩と普及も、ネットワーク社会の実現に大きく寄与することになる。第一、第二は大きく関連している。
そして、ヒューマン・ウェブ以前にCOVID-19が問うのは自然と人間の関係である。ウィズ・ウイルスの時代というけれど、そもそも、ウィズ・ウイルスの生態学的基盤を大きく崩し続けてきたのは人類の方である。 「平成」時代に危機的な問題として浮かび上がったのは地球環境問題であり、世界人口の爆発的増加である。しかし、その解決へ向かうパラダイム・シフトは必ずしも起こってはこなかった。地球温暖化対策に各国の取り組みが積極的ではないことは、スウェーデンの若き環境活動家グレタ・トゥーンベリが厳しく告発するところである。COVID-19が、果たして、大きな方向転換をもたらすかどうかは、まさに現在の問題である。
6 実験室的状況においての感染確率は当たり前のように思えるし、夜の街だとか居酒屋、カラオケなどが、感染確率が高いなどというのはあまりにも杜撰なように思える。

図4 夜の地球 NASA
― ウィズ・ウイルスの世界
COVID-19は、住居のあり方について実に多くのことを突きつけるが、感染と空間の気密性、密度、社会的距離と感染確率といった問題はここでは置こう6。COVID-19の感染状況は、実に多様なヒューマン・ウェブのあり方を示している。各国、各自治体の対応も実に多様である。ウィズ・ウイルスの体制として、それぞれの保健体制、医療体制など行政システムの全体が問われている。国や自治体を率いる首長の力量が問われ、露わになりつつある。
かつて、といっても大昔のことであるが、住居とその近傍は、教育、医療など人間生活のほとんど全てが行われる場所であった。やがて、といっても産業革命以降といっていいのであるが、住居とは別に学校、病院といった公共施設が成立する。住居と職場が分離し、さらに、長い通勤時間のかかる大都市が成立してきた。COVID-19がまず突きつけたのは、職場と住居の距離である。テレワーク、オンライン会議の導入によって、通勤の時間と空間が問い直されることになった。そして、ステイ・ホームによって意識されるのは住居そのものの質である。在宅勤務はテレワークのための設備を必要とする。ホームオートメーション、インテリジェントハウス、電脳住宅、マルチメディア住宅、IT住宅などと呼ばれて、情報伝達技術ICTの居住空間への導入が図られてきたが、日本の驚くほどの立ち遅れが明らかになった。住居への滞在時間が長くなり、滞在人数が多くなることにおいて、多様な行為のための空間、単純には広さ、が欲求されるのは当然である。住居周辺の近隣環境についても同様である。散歩したり、ジョギングしたり、身体を動かす空間が必要とされるのも当然である。そして、高気密高断熱も、それなりに問い直されるだろう。高気密高断熱の巨大な集合空間、例えば、タワーマンションは即否定されるのではないか。
しかし、基本的な問題は、直接場を対面で共有する人と人の関係のネットワークとその密度である。人類の歴史は,地球全体を人工環境化していく歴史である。人類が地球上に自らのエクメーネ(居住域)としてきた空間の拡がりは、都市とそのネットワークが地球全体をウェブ(蜘蛛の巣)状に覆っていく過程としてイメージされるが、その形状に致命的な問題がある。人とその集団の移動と共に交換されるのは食糧、物資、情報だけではない。ウイルスもまた交換されるのである。ウイルスの感染状況によって浮かび上がるウェブ状の分布図には、ヒューマン・ウェブの未来の形状についての示唆が含まれているはずである7。今のところ根拠無き直感に過ぎないけれど、自律(隔離)可能な居住域(世界単位)、一定規模の集住単位(都市)の分散的配置、地域居住単位の自然との共生が基本的指針となることはCOVID-19以前から変わらないと思う。
7 本稿を書いた後、第33回 AF-Forum「ポストコロナの暮らしと仕事、住まいと都市」コーディネーター:和田章 パネリスト:田辺新一(早稲田大学)、山中大学(総合地球環境学研究所(2020年8月21日))に参加した。COVID-19について多くの知見を得たが、山中大学先生の「COVID-19に顕在化した人間活動偏在による災害環境リスク」にはわが意を得たりであった。モデルは極めて単純である。飛沫感染する空間は、人類起源の最小規模の大気環境であろう。いわゆる社会距離は単純には人口密度である。ジャカルタと東京の比較など、グローバルな視点によるマクロな分析結果は説得力があった。人間居住の偏りが問題であり、江戸時代の藩の編成がモデルになるという。これを掘り下げたいが、今回は紙数がない。引き続き考えたい。
参考文献
・布野修司+田中麻里+ナウィット・オンサワンチャイ+チャンタニー・チランタナット(2017)『東南アジアの住居 その起源・伝播・類型・変容』京都大学学術出版会
・Guidoni, E.(1975), “Architettura Primitiva”, Electa, Milano(Guidoni,E.(1979)”Primitive Architecture”, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, New York :ギドーニ, エンリコ(2002)『原始建築』桐敷真次郎訳,本の友社)
・ラポポート, A.(1987)『住まいと文化』山本正三他訳,大明堂(Rapoport, A.(1969), “House Form and Culture”, Engelwood Cliffs, Prentice-Hall)。
・吉見俊哉(2019)『平成時代』岩波新書
・マクニール,W.H.(1985)『疫病と世界史』佐々木昭夫訳,新潮社(上下,中公文庫,2007)
・マクニール,W.H.・マクニール,J.R.(2015)『世界史 人類の結びつきと相互作用の歴史』Ⅰ,Ⅱ,福岡洋一訳,新潮社
布野修司 Shuji FUNO
Born in 1949, Dr. Shuji Funo graduated from the University of Tokyo in 1972 and became an Associate Professor at Kyoto University in 1991. He is currently a Project Professor at Nihon University. He has been deeply involved in urban and housing issues in South East Asia for the last forty years. He is well recognized in Japan as a specialist in the field of human settlement and sustainable urban development affairs in Asia. His Ph.D. dissertation, “Transitional process of kampungs and the evaluation of kampung improvement programs in Indonesia” won an award by the AIJ in 1991. He designed an experimental housing project named Surabaya Eco-House and in his research work, he has organized groups on urban issues all over the world and has published several volumes on the history of Asian Capitals and European colonial cities in Asia. Apart from his academic work, he is well known as a critic on architectural design and urban planning.