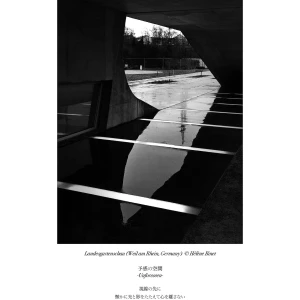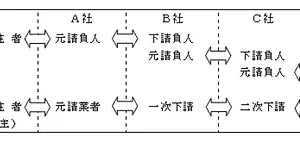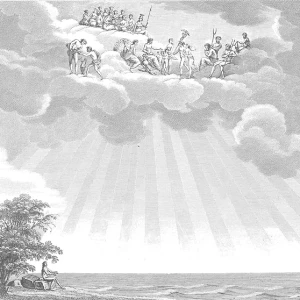「アジア」の欠落 ― 世界建築史をいかに書くか?|布野 修司
先ごろ『世界建築史15講』(彰国社、2019年4月10日)という一冊の本(共著)を上梓した(図①)。タイトルが示すように、15回の講義(Lecture01〜15) を想定した教科書のスタイルである。それぞれにコラム(Column01〜15)を付し、計30本(章節)の原稿(4〜12頁)からなる。編集委員会編というかたちをとったが、実質、布野修司、青井哲人、中谷礼仁の三人(幹事)で、全体構成、執筆者を考えた。建築史の専門家は一般的に筆が遅い。一行を書くのにも裏付けが必要で、時間がかかるのである1)。案の定、思うように原稿が集まらず、僕は、責任をとるかたちで、30本中9本の原稿を書く羽目となった。だけど、僕にはこの一冊に拘る理由があった。
京都大学時代(1991〜2005)に遡る。アジアを随分歩いているのだから「世界建築史Ⅱ」を担当するようにと西川幸治先生に命じられたのである。「Ⅰ」が「西欧」、「Ⅱ」が「非西欧」である2)。当時、『東洋建築図集』(1995)の東南アジアの章の幾頁かを執筆したばかりであった。この際「アジア」の建築を勉強するか!と、講義を続けながら、『東洋建築図集』に取り上げられた建築を機会ある度に見て回った。現在までに『図集』に掲載された建築の90%以上実見したのではないか?そし て、アジア都市建築研究会の仲間たちと『アジア都市建築史』(布野修司編、昭和堂、2003)をまとめるにも至った。しかし、何故「アジア」に限定されるのか?、 何故「世界建築史」の「Ⅱ」なのか?、しっくりしてこなかったのである。
1) 本書のもとになったのは、『世界建築史図集』あるいは『グローバル建築史事典』といった世界中の建築を網羅する資料集あるいは事典の構想である。しかし、そうした建築史集成や体系的な建築史叙述は未だ蓄積不足で、時間もかかることから、まず、グローバルに建築の歴史を見通す多様な視点を示すことを優先したのであった。
2) 京都大学には、建築学科一期生村田治郎の学位論文『東洋建築系統史論』に始まる「東洋建築史」という科目があった。しかし、戦後、「東洋建築史」という科目は日本の建築学科から―京都大学を除いて―なくなる。 日本の建築界は欧米一辺倒となるのである。 戦後、建築ジャーナリズムにおいてアジアの建築に触れたのは、「天壇」「宗廟」について書いた白井晟一ぐらいである。僕は、東京大学で太田博太郎、稲垣栄三先生から建築史を教わったけれど、「東洋建築史」については聴いた記憶がない。京大隊の一員としてガンダーラで発掘作業に携わってきた西川先生に は、「東洋建築史」を「世界建築史II」として存続させたい、という強い思いがあった。

図①『世界建築史 15 構』カヴァー
― 蘭領東インドの H.P. ベルラーヘ
洋の東西を区別しない「世界建築史」の必要性を最初に意識したのは、スラバヤ(拙稿「ある都市の肖像―スラバヤの起源」『traverse19』参照)を訪れて、「オランダ近代建築の父」と言われるH.P.ベルラーヘの作品(生命保険年金協会AMLLビルKantoor van de ‘Algemeene Maatschappij voor Levensverzkering en Lijfrente’、1900)(図②abcd)に出会った1982年である。その建設は、代表作「アムステルダム証券取引所」(1910)(図③abc)に10年先立っている。
ベルラーヘとアムステルダム・スクールの建築家たちに惹かれて、堀口捨巳の『現代オランダ建築』(1930)を片手に見て回ったのは1976年であるが、ベルラーヘの作品がインドネシアにあることなど全く知らなかった3)。考えて見れば、オランダがインドネシアを植民地としたのは17世紀初頭であり、300年以上、自らの「世界」であったのだから、オランダの建築家がインドネシアで仕事をするのは不思議でも何でもない。調べてみると、インドネシアで活躍したすぐれた建築家は少なくない。その代表がデルフト工科大学(T.H.Delft)卒業の同級生H.M.ポントHenri Maclaine Pont(1884-1971)とH.Th.カールステン(1884-1945)である。少なくとも、この二人は、同世代のG.T.リートフェルト(1888-1964)やJ.J.P.アウトOud(1890-1963)と同等に評価すべき建築家である。H.M.ポントは、「バンドン工科大学」(1918、図④abcd)の設計で知られるが、「ポサランの教会」(1936、図⑤abcd)が特にすばらしい。
H.P.ベルラーへは、1923年に初めてオランダ領東インドを訪れ、後年『私の印度旅行― 文化と芸術に関する考察― 』(Berlage、 H.P.、1931)を出版する。5ヶ月にわたる旅行の目的は、オランダ本国政府のアドヴァイザーとして、プランバナン遺跡群の修復について報告書を作成することであった4)。H.P.ベルラーへは、そこで、プランバナンのロロ・ジョングランなどヒンドゥー建築の遺構を「死んだ伝統」として評価していない。そこには、当時のヨーロッパ人建築家のアジアの伝統建築に対する一般的見方をうかがうことができる。ベルラーヘが高く評価したのは、H.M.ポントやH.Th.カールステンの作品である。東インドにおける伝統的建築の「生きた」伝統とヨーロッパの新しい建築すなわち近代建築をいかに統合するかが、H.M.ポント、H.Th.カールステン、そしてH.P.ベルラーヘの共有するテーマであった。
その後、東南アジアから南アジアへ、さらにアフリカやラテンアメリカにも足を伸ばし、「世界」を股にかけて活躍した建築家たちとその作品群を知ると、「世界建築史」の必要性をますます強く意識するようになったのである。
3) AMLLビルは、オランダ領東インドで活動していたM.J.フルスィットHulswit(1862 ~1921)に依頼された設計案について意見を求められ、「ヨーロッパの建築をそのまま適用したもので拒絶せざるを得ない」と批判したことから、結果的にベルラーヘの案が採用されたのが経緯である。ベルラーへは、さらに、本国で多くの支社事務所を設計していたネーダーランデン保険会社De Algemeene Nederlanden van 1845のバタヴィア本部の設計(1913)にも関わっている。いずれも設計のみへの関与で現地での施工監理を行ったわけではないが、現地の事情には通じており、東インドの若い建築家たちへの影響力は大きかったと考えられる。
4)37 葉のスケッチが掲載されているが、スラバヤについては、カリマス沿い、中国廟、アラブ街の三葉のスケッチが掲載されている(図⑥abcd)。

図②-a

図②-b

図②-c

図②-d

図③-a

図③-b

図③-c

図④-a

図④-b

図④-c

図④-d

図⑤-a

図⑤-b

図⑤-c

図⑤-d

図⑥-a

図6-b

図⑥-c

図⑥-d