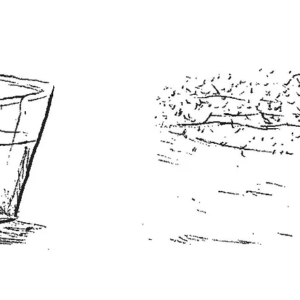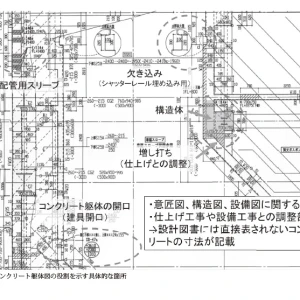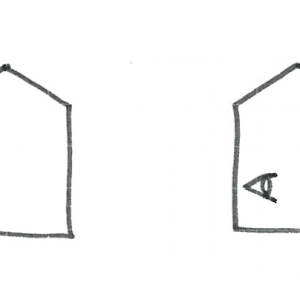津波ゲーティッド・コミュニティー|牧紀男
Tsunami Gated Community
― 東日本大震災の復興と防潮堤
東日本大震災の復興では、被災した地域を津波に対して安全に再建するため、防潮堤、堤防として機能する盛土上の道路、高台の住宅地、盛土の上のまちが建設されている。震災から6 年が経過し10 mを超えるような防潮堤・盛土の上のまちが姿を現しつつある。5 年で応急仮設住宅が解消された阪神・淡路大震災と比べると復興事業の完了に時間がかかっているが、ようやく再建されたまちの姿が見えてきた。その一方で再建された新しいまちに人が戻ってこないという問題も発生している。
災害復興の基本は「二度と同じ被害を繰り返さない」ということにある。日本の災害対策の基本方針を示す「災害対策基本法」に「この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため( 第一条)」とあり、被害とは「国土、生命・身体、財産」に対するものであると規定される。復興に際しても、命は当然のこととして、財産である建物も同じ被害を受けないようにすることが基本条件となる。関東大震災(1923)、宮城県沖地震(1978)、阪神・淡路大震災(1995)と地震災害の復興では、災害の教訓を踏まえ構造物の耐震性能の向上がはかられてきた。阪神・淡路大震災では1981 年以前に建設された建物の倒壊により多くの人命が失われたことから、その反省を踏まえ古い耐震基準で建設された建物の更新・補強が促進され、さらに2000 年の建築基準法の改正では検査制度の改善・木造建築物の耐震基準の強化が行われた。また、第二次世界大戦で空襲を受けずに残った密集市街地では延焼火災による被害も発生し、被害を受けた地域の復興では土地区画整理事業が行われ、再度、延焼火災が発生しないように道路の拡幅・公園の整備が行われた。
しかし、東日本大震災の場合、東北太平洋沖地震(M9)と同じ規模の津波に襲われると、復興事業が完了したとしても財産に対する被害は発生する。命・財産も含めて「二度と同じ被害を繰り返さない」ということは東日本大震災の復興では実現されていない。L1 クラスと呼ばれる発生頻度の高い津波に対しては「人命・財産を守る」というこれまでの方針が踏襲されているが、東日本大震災を引き起こしたようなL2 と呼ばれる想定される最大クラスの津波について、人命は守るが業務施設が被害を受けることはやむを得ないという考え方での復興が行われた。日本では、洪水・高潮・津波といった水災害から「堤防」でまちを守るのが基本となっている。東北太平洋沖地震(M9)クラスの津波を防ぐためには、非常に高い防潮堤が必要となり「二度と同じ被害を繰り返さない」高さの防潮堤ではなく、東日本大震災の復興では、東日本大震災以前の津波高を基準とした「低い防潮堤」でまちを守ることとなった(写真1, 2)。こういった方針転換に対して「もっと高い防潮堤を」という意見があっても良さそうであるが、それとは反対に「防潮堤が高すぎる」「堤防で海が見えなくなる」という意見が時に宮城県では大きい。

写真1 岩手県山田町の防潮堤

写真2 宮城県名取市の防潮堤
財産を守る方法として防潮堤だけでなく高台に移転・盛土という方法もあるのに対して、防潮堤建設を前提として対策が検討されるという目的と手段が逆転した検討のプロセスにも高い防潮堤が必要ないと考える原因の一端はある。何を守るのか、という根源的な問題もあり、米国には高潮で被害を受けるにもかかわらず景色を守るために防潮堤を建設しない註1 という考えかたも存在する。東日本大震災の復興で問題となった津波からまちを守る「壁」である防潮堤の意味について数十年に一回という割合で頻繁に津波に襲われてきた東北の経験から考えてみたい。
註1 防災対策には被害が発生しないように防潮堤をつくって被害を抑止( 被害抑止、mitigation) するという対策と、被災しても例えば保険で再建費用をカバーし被害を軽減する(被害軽減、preparedness)という2 つの方法が存在する。