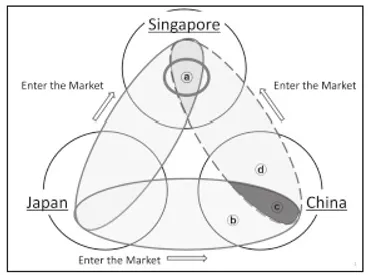
シンガポール・建設産業界との交流|古坂秀三
3.8( 仮称)大手町1-1計画A棟新築工事
□現場視察の概要
狭小過密な地域で逆打ち工法を採用した現場写真5で、既存建物の解体にはカットダウン工法で解体期間短縮と解体材の飛散防止を実現している。発注は設計と施工を分離した伝統的な方法である。
□現場視察前後に出た主な質問
「地下鉄との境壁など、地下鉄が工事に与える影響はどうか」、「立て替えで建物の高さはさほど変わらないが採算性は向上するのか」、「カットダウン工法のメリットは何か」、「逆打ち工法は技術的に安定しているのか」、「地下水の問題はどのように解決しているか」

写真5:大手町1-1計画A 棟新築工事現場

8.(仮称)大手町1-1計画A 棟新築工事
用途:業務ビル等複合施設
規模: 地下5 階・地上22 階、地下SRC 造・地上S造(柱CFT)、制震構造、建築面積4,128m2、延面積
107,747m2
建築主:三菱地所・JX ホールディングス・大手町デベロップメント特定目的会社、設計者:三菱地所設計、施工者:(仮称)大手町1-1計画A 棟新築工事共同企業体(鹿島建設・NIPPO JV)
特徴:100 年存続するグレードの建物構築を目標に、再現期間150 年の設計風荷重を考慮した外壁は、石打込みのPCCW とLow-E ガラスによるダブルスキンCWを採用している。主用途は、事務所、物品販売店、飲食店、駐車場の複合用途。高度防災都市づくりに向けた取組みから、津波に対する防潮設備、停電時の室内環境確保の為の手動換気装置、6000ℓのオイルタンクと非常用発電装置などを設置している。さらに、隣接する皇居濠の浄化設備施設も併設する。
工期:34 ヶ月(着工:2013.2、竣工予定:2015.11)
訪問時点での施工段階:地上鉄骨建方、低層階・地下躯体、地下外周掘削
視察内容:施工現場を訪問し、担当者から説明聴取、現場を見学
3.9 日本建設業連合会でのレクチャー3
□レクチャー3の概要
レクチャーは3人で分担された。①日本建設業連合会の活動について、②日本の建設生産性向上への計画と1 つの事例、③海外での土木工事の事例紹介写真6
□レクチャー後に出た主な質問
「生産性向上の指標はどのようなものがあるか」、「建設産業界への入職者が減っているがその対策は?」、「新卒者の初任給は?」、「入社後の教育システムはどうなっているか」、「女性技術者の増加と活用策にはどのようなものがあるか」

写真6:日本建設業連合会でのレクチャー
3.10 清水建設本社10 とレクチャー4
□現場視察・レクチャー4の概要
工事中から、節電・省エネ対策、非常時の事業継続・エネルギー確保のために様々な新技術が組み込まれているとして注目された建物の見学とその内容のレクチャーである写真7。
□現場視察・レクチャー後に出た主な質問
「節電・省エネ等の監視システムはどのようになっているか」、「現在の技術水準に至るまでの歩みはどのようなものであったか」、「日本でのこれらの評価のしくみはあるか」

写真7:清水建設本社でのレクチャー

10. 清水建設本社
用途:事務所
規模:地下3 階・地上22 階・塔屋1 階、RC 造、免震構造、延床面積約51,800m2
建築主:清水建設、設計/施工者:清水建設
特徴:平常時の節電・省エネ対策と非常時の事業継続・エネルギー確保を目指すecoBCP の概念にもとづき、免震RC 超高層コラムレスオフィスをもとに太陽光発電パネルを搭載したハイブリッド外装システム、タスク&アンビエンド輻射空調・LED 照明、スマートBEMS 等の環境技術を駆使することにより、一般的なオフィスビルに対しCO2 排出量を62% 削減(CASBEE S ランク、LEED ゴールド認証を取得)
工期:37 ヶ月(着工:2009.4、竣工:2012.5)
訪問時点での施工段階:施工済
視察内容:本社ビルを訪問し、会議室にて担当者から本社ビル建設プロジェクトについてのレクチャー(Lecture4)、ビル内外の見学
3.11 清水建設技術研究所11 とレクチャー5
□現場視察・レクチャー5の概要
「建設界の革新に向けた生産性向上のための研究開発活動」と題して、建設産業での生産性向上は地道な研究開発活動から生まれるもので、決して一夜にしてすばらしい技術が生まれるものではない。その30 年余りの変遷を振り返り、将来への展望をレクチャーされた図8。
□現場視察・レクチャー後に出た主な質問
「要素技術にはどのようなものがあり、それはどのような経緯から生まれたか」、「自動化施工で開発された要素技術は、その後どのようなものに応用されているか」

図8:建設界の革新に向けた将来への展望

11. 清水建設技術研究所
用途:研究施設
規模:敷地面積約21,000m2
建築主:清水建設、設計/施工者:清水建設
特徴:同研究所は、大型構造実験棟、材料実験棟、風洞実験棟、振動実験棟、音響実験棟など12 の先端実験施設を有する都心型建設技術研究所として、基盤技術の高度化研究を実施するとともに、総合的なソリューション提供のための応用研究開発を他産業企業や研究機関等とのオープンイノベーションにより推進。
工期:14 ヶ月(着工:2002.9、竣工:2003.10)
訪問時点での施工段階:施工済
視察内容:研究開発の重点領域である生産革新分野の研究概要及び建築設備一体等のユニット化における標準化とICT 活用に関する事例説明(東京モード学園、清水建設新本社等)(Lecture 5)と部材・材料のリユース・リサイクル技術を適用した施設見学
3.12 竹中工務店東京本店12 とレクチャー6&7
□現場視察・レクチャー6&7の概要
約10 年前に建設されたこのビルは、当時の環境共生技術、省エネ技術等を数多く取り入れるとともに、建設に当たっては生産設計上の成果を最大限生かしたものとなっている。そのためのレクチャーとして次の2つを用意した。① 1980 年代以降の日本と星国のプロジェクトのマネジメントについて、②東京本店プロジェクトについて写真8、図9
□現場視察・レクチャー後に出た主な質問
「マネジメントにおける日本と星国の違い、星国へのアドバイス」、「3D プリンターなどが喧伝されるがどう考えるか」、「工期、予算が厳しいプロジェクトをどうマネージするか」、「人材不足の中での短工期工事ではどう工夫しているか」、「革新的手法とは何か」

写真8:竹中工務店東京本店でのレクチャー

図9:複合化工法について

12. 竹中工務店東京本店
用途:事務所
規模:地上7 階、塔屋1 階、S造(柱CFT)、延面積
29,749.96m2
建築主:竹中工務店、設計/施工者:竹中工務店
特徴:設計施工一貫システムにより、最新の建築技術を随所に取り入れ、“ 知的生産性を向上させるワークプレイス” と、環境負荷が小さく、コストパフォーマンスの高い“ サステナビリティ建築” を追求した本社ビル。10.8m × 10.8m の均等スパンと外殻ブレ-スによる架構計画、光の運河による自然光取り入れ、自然風利用のハイブリッド空調等々の要素は、施工性にも優れ、同社の手がける様々な事務所建築のプロトタイプとなっている。
工期:12 ヶ月(着工:2003.10、竣工:2004.9)
訪問時点での施工段階:施工済
視察内容:本社ビルを訪問し、会議室にて担当者から本社ビル建設プロジェクトについてのレクチャー(Lecture6)、ビル内外の見学
3.13 南池袋二丁目A 地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築他工事13
□現場視察の概要
低層部に防災拠点としての区庁舎を有する大規模な集合住宅で、工事は積層工法で行われた。設計と施工は分離して発注された写真9。
□現場視察前後に出た主な質問
「現場での労働時間等と近隣との合意について」、「積層工法のサイクル工程であるが、なぜ4サイクルがよいのか」、「一般階での柱、梁、スラブ等の数量」、「工事中の足場の盛り替えについて」、「使用しているPC 工場、生コン工場の数と分布」

写真9:南池袋2 丁目A 地区市街地再開発事業での説明

13. 南池袋二丁目A 地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築他工事
用途:住宅、庁舎(豊島区役所)、店舗、事務所規模:地下3 階・地上49 階、SRC・RC 造、延床面積94,800m2
建築主:南池袋二丁目A 地区市街地再開発組合、設計者:日本設計、施工者:大成建設
特徴:①行政が庁舎建て替えにあたり民間活力を活用して新たな街づくりを実現した代表的な事例。②低層部が防災拠点としての機能を有する豊島区庁舎、高層部が共同住宅、地下では地下鉄駅に連絡する等、都市インフラ機能を有する。③低層部の外装パネルや高層住戸のバルコニー手摺に太陽光パネル、緑化パネルを配するとともに、低層部には水の流れる屋上庭園を整備し、省エネや環境に配慮。④高層直下部に逆打ち工法を用いており、高強度PCa(Fc=140N/mm2)の構真柱とすることで断面・重量を軽。そのまま本設柱として活用できるため更なる工期短縮が可能。⑤ 12 ~ 49 階にRC 積層工法を用い、1 フロア4 日のサイクルで工期を短縮。工期:37 ヶ月(着工:2012.2、竣工予定:2015.3)訪問時点での施工段階:地上躯体を完了し、内・外装・仕上工事中視察内容:施工現場を訪問し、担当者から説明聴取、現場を見学
3.14 東京スカイツリー14 とレクチャー8
□現場視察・レクチャー8の概要
東京スカイツリーの設計、施工の記録に基づき、その建設過程の説明と、実際の建物の見学を行った写真10、図10。
□レクチャー後に出た主な質問
「安全上の工夫、とりわけ塗装の塗り替え時のことをどのように考えているか」、「タワークレーンのクライミングと解体の方法」、「火災時の避難経路、制御等について」、「溶接工を数多く必要としたが、その手配をどうしたか」、「スチールの強度はどうか」

写真10:東京スカイツリーでのレクチャー

図10:東京スカイツリーの施工

14. 東京スカイツリー
用途:自立式電波塔、展望施設(第一展望台350m/ 第二展望台450 m)
規模:高さ634 m、S・SRC・RC 造、重さ約36,000t(タワー鉄骨総重量)、約2,900 人収容
建築主:東武鉄道・東武タワースカイツリー、設計者:日建設計、照明コンサルタント:シリウスライティングオフィス、施工者:大林組
特徴:外観は、足元が正三角形で、上へ伸びるにつれ円へと連続的に変化し、見る角度や眺める場所によって多様な表情を持っている。施工にあたっては、自立式電波塔世界一の高さを支える基礎杭にナックル・ウォールを採用するとともに、心柱制振を用いてタワーの揺れの軽減を図っている。最上部となるゲイン塔(長さ200 m)は、低層部で施工の上、心柱の空間部分を利用してリフトアップする工法を採用するなど、技術の粋を結集している。
工期:44 ヶ月( 着工:2008.7、竣工:2012.2)
訪問時点での施工段階:施工済
視察内容:東京スカイツリーイーストタワーでの事前説明(Lecture 7:スカイツリープロジェクトの概要及び施工上の工夫等)及びスカイツリー展望台の見学
― 4. おわりに
5日間の同行は予想外にハードであった。しかし、訪日団の視察の様子、Q&A の時の矢継ぎ早の質問、その質問の内容の素直さ・真剣さには目を見張るものがあった。欲を言えば、初日にレクチャーした観点「安定した建築生産システムの構築、優れた技術者/技能者の育成等の結果であり、生産性向上等の前に安全、高い品質等の確保が重要であるので、今回の視察ではそれらの点を十分に理解してもらいたい」がもう少し反映した視察であってほしかった。しかし、この訪日を契機として、国土交通省とBCA、あるいは団体間ならびに企業間、個人的にも交流の輪が広がれば望外の喜びである。







