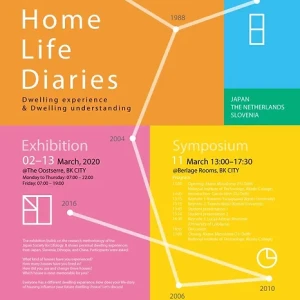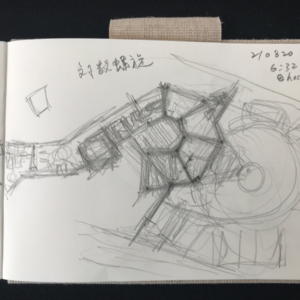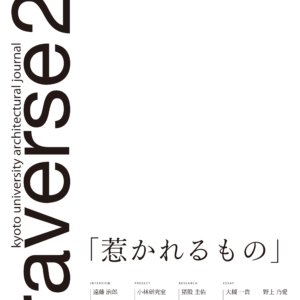中井 茂樹|ロベール・ブレッソン論-生きつづける関係-
― 関係への遡行
存在と事物が、生きてゆくために待ち望んでいる絆の数々。7
手始めにブレッソンの映像に表現される人物や事物の“ 存在” について論じた。では、それらの“ 存在” をブレッソンはどのように関係づけているのであろうか。ブレッソンの映画を紐解くに際し、“ 境界” という概念を端緒に考察を試みる。
唐突ではあるが、映像は“ 境界” をつくるものと言えるであろう。キャメラの枠は世界を切りとる“ 境界” となる。この映像における“ 境界” の考え方を建築に敷衍するならば、敷地境界線はひとつの“ 境界” と捉えられるかもしれない。
そして“ 境界” が存するということは、そこに“ 関係” が生まれる。我々は意図をもって切りとられた“ 境界” の映像をみて、そこに含まれなかった“ 境界” の外側を思い遣ることができる。我々は“ 境界” のこちら側とあちら側の間に、“ 関係” を見出すことができる。
加えて、異なる“ 境界” の映像を繋ぎ合わせるモンタージュの手法は、現実には強く意識することのない人物や事物の“ 関係” を詳らかにするであろう。
“ 境界” は密接に“ 関係” と結びつく。これは映画芸術全般に通ずる本質的な “ 境界” の捉え方である。
続いて、ブレッソンが映像を構成している要素としての “ 境界”、橋と扉を取り上げてみたい。
ゲオルク・ジンメルは「橋と扉」(1909)という論考のなかで、扉という事物が有する意味について次のように述べている。
扉はまさに開かれうるものでもあるがゆえに、それがいったん閉じられると、この空間の
かなたにあるものすべてにたいして、たんなるのっぺりとした壁よりもいっそう強い遮断
感を与える。壁は沈黙しているが、扉は語っている。8
『ラルジャン』(1983)では、扉の開閉による映像の切り替えが顕著にみられる。
人物が扉を越境して次の空間に移動し、扉が閉じられることで映像が切り替わる。そして人物が移動した先の空間にキャメラが移り、次の映像が映し出される。キャメラは人物と同じように扉を越境するのではない。そこには映像としての断絶が生まれ、同時に時間的にも断絶が生じている。
つまり扉という“ 境界” は、「自然的存在の画一的で連続的な一体性をいかに分離するかを示している9」のである。ブレッソンは映像の切り替えに扉という要素を用いることで、視覚的にも意味的にも映像の“ 関係” の変化を強調して表現していると言える。
このような分離の“ 境界” として特筆しておきたいのが、川島雄三の映画『しとやかな獣』(1962)である。川島は団地の一室を舞台に、登場人物の心的関係を空間に穿たれた“ 境界” を介することで巧みに描き出している。
一方、橋はどうであろうか。ブレッソンは『白夜』(1971)において、橋を2つの“ 境界”を表象するものとして扱っている。
橋がひとつの審美的な価値を帯びるのは、分離したものをたんに現実の実用目的のために結合するだけでなく、そうした結合を直接可視化しているからだ。10
『白夜』では、男女がはじめて出逢い、そこに“ 関係” が生まれる場所として橋が設定されている。
藤沢周平の小説『橋ものがたり』(1980)は橋に纏わる短篇集であるが、藤沢も橋を、人と人、場所と場所を繋ぐ “ 境界” と捉え、互いを慮る“ 関係” の物語を描いている。
「事物は、一緒になるためにはまず離れ離れにならなければならない11」。橋はその分離を結合する“ 境界” として機能するのである。
そしてもうひとつは、生と死の“ 境界” としての橋である。『白夜』において、橋は生と死の狭間を揺れ動く場所でもある。橋という“ 関係” としての“ 境界” が、生(結合)への執着と死(分離)への希求とを相乗的に齎しているとも考えられるであろう。
我々はブレッソンの映画に描かれる橋と扉に、隠喩としての“ 境界” を見出すのである。
さて本題に入ろう。ブレッソンが人物や事物の“ 存在” に漸近することによって見出される“ 境界” とは如何なるものであろうか。
“ 存在” への漸近とは、つまるところ本質を掴み取り原型へと至る志向性のことであった。ブレッソンの禁欲的な表現手法、我々はそこに両極としての“ 境界” を見出す。それは、極めて物質に肉薄し相対する“ 関係” としての“ 微視的境界” と、極めて精神に肉薄し相対する“ 関係” としての“ 巨視的境界” である。“ 微視的境界” は人物や事物の運動だけをクロースアップで捉えるブレッソンの姿勢に貫かれており、“ 巨視的境界” はブレッソンが一貫して自らの映画の主題に取り上げる悪や死といった精神性との交感に垣間見ることができる。
建築や都市にあらわれる境界は、それをめぐって、人間が生きるといった境界である。建築や都市にみられる境界の性質は、生きるうえで設定される非物的な境界一般においてもあらわれているのではないか 12
原広司も自身の「境界論」(1981)でこのように述べているが、“ 境界” とは“ 存在” が生きるために必要不可欠なものなのである。
我々はブレッソンの表現手法を通し、異なる次元で“ 存在” する人物や事物の“ 関係” を統べるものとして“ 境界” という考え方が汎用可能であることを示した。それは映画という“ 境界” を創造する芸術においてこそ、如実に見出されるものであろう。
対象と対象とが互に相関係し、一体系を成して、自己自身を維持すると云ふには、かゝる体系自身を維持するものが考へられねばならぬと共に、かゝる体系をその中に成立せしめ、かゝる体系がそれに於てあると云ふべきものが考へられねばならぬ。有るものは何かに於てなければならぬ、然らざれば有るといふことと無いといふこととの区別ができないのである。13
西田幾多郎は「場所」(1926)という論考のなかで、“ 関係” の階層構造について述べている。
“ 境界” は “ 関係” を齎すのであるが、そこで見出された“ 関係” とは果たしてそれ自体で成立するのであろうか。
西田が述べるところによると、ある事物と事物の“ 関係” はそこでの“ 関係” だけで成立しているのではなく、その“ 関係” を包括する上位の“ 関係” が更に存在する。“ 関係” とは、幾重にも階層を重ねて構造化されたものなのである。
ブレッソンの映画において見出された“ 微視的境界” と“ 巨視的境界” は、物質と精神という両極のものと“ 関係” を取り結んでいる。この両極の“ 関係” は映画のリアリティとしては受け入れられるものであるが、現実世界は両極の“ 関係” だけでは成立し得ないであろう。なぜなら我々は映像を映し出すキャメラのように現実世界を捉えているわけではないからである。
つまり我々が生きるためには、“ 関係” の階層構造を汲み、“ 関係” の解像度をその都度合わせていくことが必要となる。言うならば現実と虚構の関係も、その“ 関係” の妙において成立するのである。
反復(或る映像の、或る音の)から君が引き出すことのできるあれらすべての効果。14
ブレッソンは映画において“ 反復” を多く用いることも忘れてはならない。映画の技法上のことを考えるならば、“ 反復” は映像にリズムを齎すであろう。
[リズムの存立にとって]まず、分割されざる運動状態が不可欠であり、つぎに、できるだけ類似したものができるだけ類似して再帰することが不可欠である。15
『少女ムシェット』(1967)には印象的な“ 反復” の映像がある。物語の主人公は最後に自ら死を選択するのであるが、ブレッソンはこのシーンを原作の小説とは異なる描写で描き出している。主人公は3度斜面を“ 反復” するように転がり、そして漸く3度目に池のなかに落ち、音と水面の波紋によってそのことが示される。
我々はここに“ 反復” による生と死の葛藤を見出すであろう。そして、生きる“ 関係” とは“ 反復” によって齎されると敷衍することはできないであろうか。ブレッソンは死への対比として、少女の生きる姿を“ 反復” によって表現している。すなわち生きることとは、“ 反復”による“ 関係” の確認行為なのである。
同様のことは、音楽の“ 反復” に置き換えて考えると分かりやすいかもしれない。自分が心地良いと感じて耳にしている曲は、必ず曲の終わりを迎える。しかしその瞬間に曲が自らのなかで終わりを迎えたと言い切れるであろうか。ある曲との“ 関係” は、変化する自身との“ 反復” 的な関わり合いによってその都度見出されるものではないか。生の永続性とは、再帰的な“ 関係” にこそ見出されるのである。
そこで“ 反復” の映画として付言しておきたいのが、ポルトガルの映画監督ペドロ・コスタの映画である。ペドロ・コスタの映画にはこの“ 反復” による生への意志がありありと感ぜられる。
7. ロベール・ブレッソン 前掲書 p.107
8. ゲオルク・ジンメル『ジンメル・コレクション』 北川東子編訳、鈴木直訳 ちくま学芸文庫 1999 p.95
9. ゲオルク・ジンメル 前掲書 p.99
10. ゲオルク・ジンメル 前掲書 p.93
11. ゲオルク・ジンメル 前掲書 p.91
12. 原広司『空間〈機能から様相へ〉』 岩波現代文庫 2007 p.168
13. 西田幾多郎『西田幾多郎全集 第三巻』 岩波書店 2003 p.415
14. ロベール・ブレッソン 前掲書 p.73
15. ルートヴィヒ・クラーゲス『リズムの本質』 杉浦実訳 みすず書房 1971 p.80