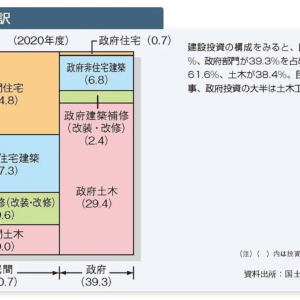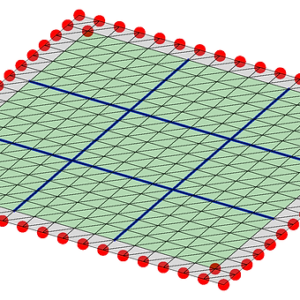中井 茂樹|ロベール・ブレッソン論-生きつづける関係-
An Essay on Robert Bresson : Subsistent Relationships
― 存在への漸近
創造すること、それは人物や事物を歪曲したりでっちあげたりすることではない。それは、存在する人物たちや事物たちの間に新たな諸関係を取り結ぶことだ、しかもそれらが存在しているままの姿で。
1フランスの映画監督であるロベール・ブレッソン(1901-1999)は、その生涯において13 の作品を自ら監督し制作している。ブレッソンの映画の特徴を端的に言い表すならば、虚飾を排した禁欲的なまでの映像表現にあると言える。ブレッソンは映像に表現される人物や事物の“ 存在” を際立たせるために、無駄な演出の一切を取り除く。ときに、削ぎ落とされた映像の“ 厳しさ” は、我々鑑賞者の感情移入を遠ざけ忌避されることも屡々あるであろう。
演劇的な、演技によって歩み寄る映画とは相反し、ブレッソンの映画が歩み寄ることはない。物語の内容が説明的に描かれるのではなく、映像固有の表現である人物や事物の“ 運動” 描写を重視し、それらを断片的に繋げ映像が進行していく。差し当たり“ 抑制された抽象性” と言葉を宛行うことも可能であろう。『抵抗 死刑囚は逃げた』(1956)では、脱獄の顛末が淡々と描かれ、『ジャンヌ・ダルク裁判』(1962)では、記録映画のように同じ構図で撮影されたジャンヌ・ダルクの裁判の映像が多くを占める。
「捜すことなく見出すという戒律を実践する2」映画。ブレッソンの映画は、ただ構え、そこに在る。我々は、映像に歩み寄らねばならない。ブレッソンの映画はそのようにして成立している。
ブレッソンは自身の映画を“ シネマ” と呼ばず、“ シネマトグラフ” と称する。シネマトグラフとは、19 世紀末にリュミエール兄弟が発明した撮影・映写一体型の装置の名称である。リュミエールがシネマトグラフを用いて最初に上映した映画は、工場の出口や列車の到着といった日常的な光景を撮影したものであった。リュミエールは凡そスペクタクルとは捉え難い“ 現実の反映” が人々を惹きつけると考えた。つまるところ当時の観衆が魅了されたものとは、工場の出口や列車の到着の“ 映像” そのものに他ならなかった。3
「シネマトグラフとは、運動状態にある映像と音響とを用いたエクリチュールである4」とブレッソンは記している。『スリ』(1959)における手の流麗な動き、『湖のランスロ』(1974)における騎馬の躍動。シネマトグラフが果たした“ 運動媒体を映像に捉える” という原初的な目的をブレッソンは意識的に自らの映画に反映させており、“ シネマトグラフ” という名称で語るのである。
「俳優なし。(俳優への演技指導なし。)配役なし。(役柄の研究なし。)演出なし。では何があるのか。人生のなかから掴み取ってきたモデルを使うこと、これだ。見せかけること(俳優)ではなく、在ること(モデル)5 」。
ブレッソンは演者を“ 俳優” と呼ばず、“ モデル” と称する。『田舎司祭の日記』(1950)以降の11 作品においては職業俳優を用いておらず、同じ“ モデル” を起用することも原則としては行わない。
抑揚のない台詞、抑制された身振り、感情を露わにしない表情。一見したところ、ブレッソンの映像における“ モデル” の振る舞いとはこのようなものであろう。なるほどブレッソンの映画に通底する主題は、悪や死といった極めて感情的なものであったはずである。
しかし、ブレッソンは徹底して即物的な表現を追究する。そこで“ モデル” に求められるものとは、“ モデル” の内にある意図や感情の表出ではなく、「外部から内部へと向かう運動」である。
重要なのは彼らが私に見せるものではなく、彼らが私に隠しているもの、そして特に、自分の内にあるとは彼ら自身思ってもいないものである。6
“ モデル” は自分が喋っていることについて考えてはならず、自分が行なっていることについても考えてはならない。運動を思考に従属させるのではなく、運動がそこに在る状態を生み出すこと。幾度も同じ台詞を繰り返し、あたかも「自動現象」のようにブレッソンは“ モデル” の台詞を抽出する。
意識の奥底に深く潜り込み、無意識へと至る発見的な漸近。そのときはじめて、“ モデル”その人物だけが有する「純粋な本質」が見出されるのである。
1. ロベール・ブレッソン『シネマトグラフ覚書-映画監督のノート』 松浦寿輝訳 筑摩書房 1987 p.21
2. ロベール・ブレッソン 前掲書 p.86
3. エドガール・モラン『映画 あるいは想像上の人間』渡辺淳訳 法政大学出版局 1983 pp.26-27
4. ロベール・ブレッソン 前掲書 p.8
5. ロベール・ブレッソン 前掲書 p.5
6. ロベール・ブレッソン 前掲書 p.6